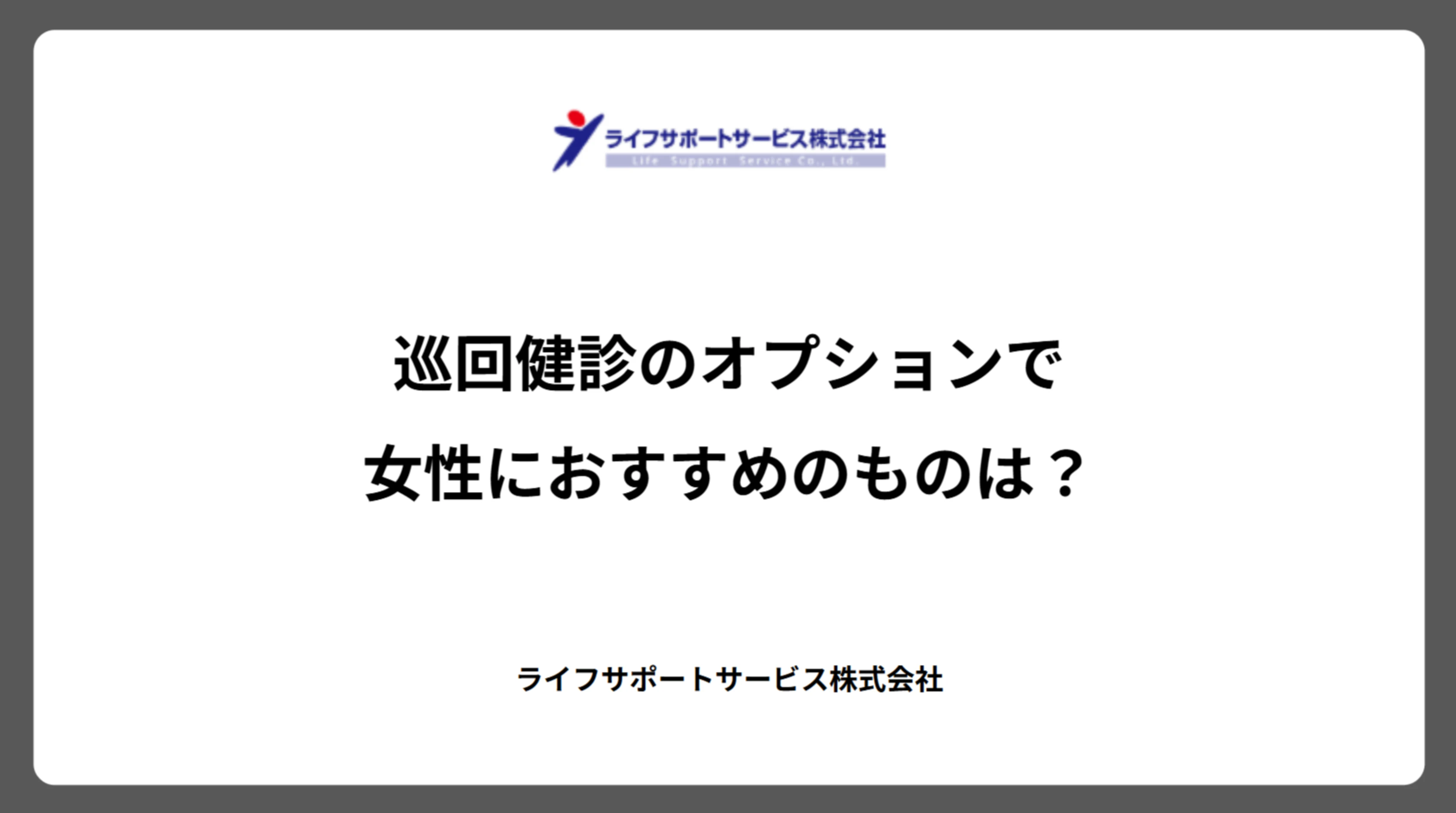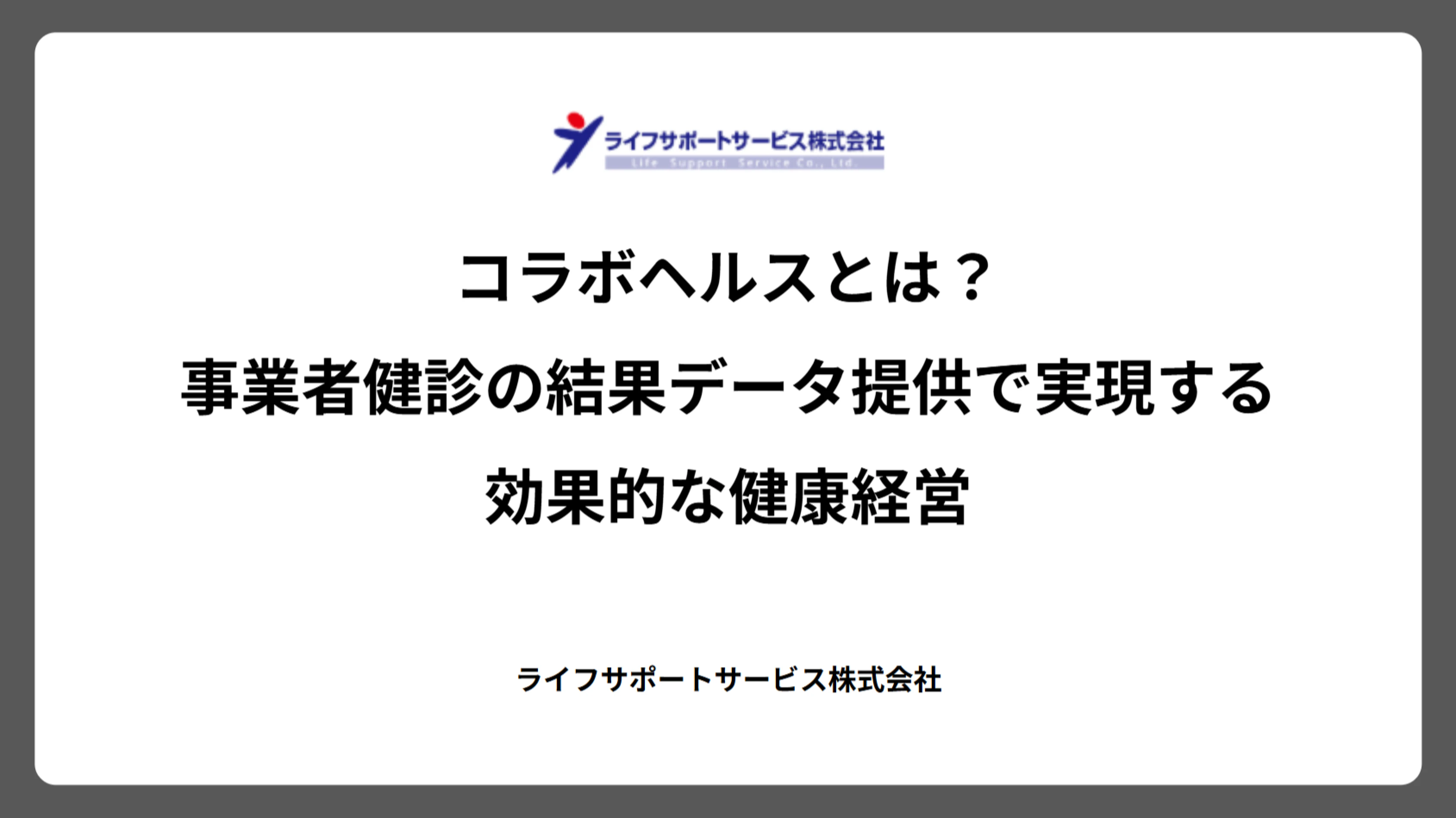記事公開日
最終更新日
健康経営優良法人とは?企業が知るべきメリットと認定取得のすべて

近年、「健康経営」という言葉を耳にする機会が増え、従業員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する企業が増えています。
国もこの動きを後押ししており、特に中小企業にとって「健康経営優良法人」の認定は、単なる表彰以上の大きな意味を持ち始めています。
しかし、「具体的にどのような制度なのか?」「認定されるとどんなメリットがあるの?」「どうすれば認定を取得できるの?」といった疑問をお持ちの健康管理ご担当者様も少なくないでしょう。
この記事では、「健康経営優良法人」とは何か、認定されることのメリット、そして認定取得のための要件や申請プロセスについて、わかりやすくご紹介いたします。
健康経営優良法人とは
健康経営優良法人制度の概要
健康経営優良法人制度とは、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する認定制度です。
この制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰することを目的としています。
企業が従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する「健康経営」に取り組むことで、従業員の健康増進だけでなく、生産性向上、企業イメージ向上、優秀な人材の確保など、多岐にわたるメリットが期待されます。
健康経営優良法人に認定されることは、その企業が従業員の健康を大切にする優良な企業であることを社会的にアピールできる証となります。
経済産業省と日本健康会議が推進する背景
健康経営優良法人制度が推進される背景には、日本が直面する社会課題があります。
少子高齢化による労働力人口の減少や医療費の増大は、企業の持続的な成長にとって大きな懸念事項です。
このような状況において、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、健康への投資を通じて企業の競争力強化を図るという考え方が広まってきました。
経済産業省は、企業の健康経営を支援することで、産業競争力の強化と経済の活性化を目指しています。
一方、日本健康会議は、国民一人ひとりの健康寿命の延伸と医療費の適正化を目標に、多岐にわたる団体が連携して活動しています。
両者が連携し、健康経営の普及と定着を強力に推進することで、社会全体の活力向上に貢献しようとしています。
健康経営とは何か 健康経営優良法人との関係
「健康経営」とは、企業が従業員の健康を重要な経営資源と捉え、健康保持・増進を経営戦略として実践することです。
これは単なる福利厚生ではなく、従業員の健康状態が企業の生産性や業績に直結するという考え方に基づいています。
具体的な取り組みとしては、定期健康診断の確実な実施、運動機会の提供、メンタルヘルス対策、長時間労働の是正、禁煙推進などが挙げられます。
健康経営優良法人は、この「健康経営」に積極的に取り組む企業を、認定する制度です。
つまり、健康経営を実践している企業が、その取り組みを外部に「見える化」し、社会的な信頼を得るための証となります。健康経営を通じて従業員の健康と活力を向上させることが、結果として企業の持続的な成長と発展に繋がるという関係性があります。
健康経営優良法人認定が企業にもたらすメリット
健康経営優良法人に認定されることは、企業にとって多岐にわたるメリットをもたらします。
単なる福利厚生の充実にとどまらず、企業の持続的な成長と競争力強化に直結する重要な投資と位置づけられます。
企業イメージ向上とブランディング効果
健康経営優良法人に認定されることは、企業が従業員が健康であることの重要性を理解し、積極的に取り組んでいる証となります。
これにより、社会的な信頼と企業イメージが飛躍的に向上します。
特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が注目される現代において、「S」(社会)の側面で従業員の健康を重視する姿勢は、投資家や顧客、取引先といった多様なステークホルダーからの評価を高めます。
結果として、企業のブランド価値が向上し、競争優位性を確立する上で大きな強みとなります。
優秀な人材の確保と定着
健康経営優良法人認定は、採用市場において企業の魅力を高める強力な要素となります。
健康的な職場環境や従業員への配慮を重視する企業として認知されることで、優秀な人材からの応募が増加し、採用競争力を強化できます。
また、従業員が健康で安心して働ける環境は、エンゲージメントの向上につながり、結果として離職率の低下にも貢献します。
従業員の定着は、採用コストの削減だけでなく、長年の経験と知識を持つベテラン社員の流出を防ぎ、組織全体の生産性維持に不可欠です。
従業員の生産性向上と業績貢献
従業員の健康状態が改善されることは、企業全体の生産性向上に直結します。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
プレゼンティーイズムの改善
体調不良を抱えながら出勤・勤務している状態(プレゼンティーイズム)が改善され、従業員一人ひとりの業務遂行能力が最大限に発揮されます。
アブセンティーイズムの削減
疾病による欠勤(アブセンティーイズム)が減少し、安定した人員体制で業務を遂行できます。
医療費の抑制
従業員の健康増進は、企業が負担する医療費の削減にもつながります。
モチベーションと創造性の向上
心身ともに健康な状態は、従業員のモチベーションを高め、新たなアイデアやイノベーションの創出を促進します。
これらの効果は、巡り巡って企業の業績向上に大きく貢献し、持続的な成長を支える基盤となります。
資金調達や金融機関からの評価向上
健康経営への積極的な取り組みは、企業の非財務情報としての価値を高め、資金調達において有利に働く可能性があります。
近年、金融機関は融資判断において、企業の財務状況だけでなく、ESG要素を含む非財務情報も重視する傾向にあります。
健康経営優良法人に認定されていることは、企業が持続可能性を意識した経営を行っている証と見なされ、金融機関からの評価向上につながります。
これにより、以下のようなメリットが期待できます。
融資条件の優遇
一部の金融機関では、健康経営優良法人認定企業に対し、金利の優遇や融資枠の拡大といった特典を設けています。
ESG投資対象としての魅力
投資家にとって、健康経営に取り組む企業は社会的責任を果たしている企業として評価され、ESG投資の対象となりやすくなります。
これにより、企業はより有利な条件で資金を調達し、事業拡大や新たな投資につなげることが可能になります。
法人税や補助金における優遇措置の可能性
現行の税制において、健康経営優良法人認定そのものに対する直接的な法人税の減免措置は限定的ですが、間接的なメリットや特定の補助金制度が存在する場合があります。
たとえば、経済産業省は健康経営優良法人認定企業が導入する特定の健康増進設備などに対して、投資促進税制の対象となる可能性を示唆していることがあります。
また、一部の地方自治体や健康保険組合では、健康経営に取り組む企業を対象とした独自の補助金や助成金、奨励金制度を設けていることがあります。
これらの優遇措置は、企業の健康投資にかかるコストを軽減し、健康経営の推進を後押しするものです。最新の情報は、経済産業省や各自治体のウェブサイト、あるいは加入している健康保険組合等で確認することが重要です。
健康経営優良法人の種類と対象企業
健康経営優良法人の認定制度には、企業の規模に応じた部門が設けられています。
大規模法人部門と中小規模法人部門
健康経営優良法人認定制度は、企業の規模に応じて大きく2つの部門に分かれています。
これは、企業規模によって健康経営の取り組み方やリソースが異なることを考慮しているためです。
大規模法人部門
主として、従業員数が多く、比較的規模の大きな企業が対象となります。
上場企業や大企業がこの部門に該当することが多いです。
中小規模法人部門
中小企業基本法に定める中小企業が対象となります。
地域に根ざした企業やスタートアップ企業などが含まれます。
それぞれの部門で、認定基準や評価項目に一部違いが設けられており、企業の実情に合わせた形で健康経営を推進できるよう配慮されています。
ブライト500とホワイト500とは
健康経営優良法人には、さらに優れた取り組みを行っている法人を表彰する制度があります。
それが「ホワイト500」と「ブライト500」です。
これらは、健康経営優良法人の中でも特に優れた健康経営を実践している企業として、それぞれ上位500法人に与えられる称号です。
ホワイト500
大規模法人部門で、特に優れた健康経営を実践している上位500法人に与えられる称号です。
健康経営の先進的な取り組みを示す企業として、高い評価を得ています。
ブライト500
中小規模法人部門で、特に優れた健康経営を実践している上位500法人に与えられる称号です。地域における健康経営のロールモデルとなることが期待されます。
これらの称号を得ることは、企業が健康経営において国内トップレベルの取り組みを行っている証となり、企業イメージの向上や優秀な人材確保に大きく貢献します。
認定対象となる企業の条件
健康経営優良法人に認定されるためには、経済産業省が定める複数の要件を満たす必要があります。
基本的な条件は以下の通りです。
日本国内に本社を置く法人であること
海外法人や個人事業主は対象外です。
健康経営を実践するための体制が整備されていること
健康経営推進担当者の配置や、従業員の健康課題を把握しPDCAを回していく仕組みなどが必要です。
健康宣言の策定と実践
企業が健康経営に取り組むことを宣言し、従業員に周知し、その内容に基づいた具体的な取り組みを行っている必要があります。
従業員の健康課題の把握と対策
定期健康診断の実施率、ストレスチェックの実施率、喫煙率などの健康データを把握し、それに基づいた改善策を講じていることが求められます。
法定健診・ストレスチェックの実施
労働安全衛生法に基づく定期健康診断やストレスチェックを適切に実施していることが必須条件です。
情報開示への協力
認定取得後に、健康経営に関する取り組み状況やデータの一部を情報開示することに同意する必要があります。
これらの条件は、従業員の健康を経営的な視点から捉え、戦略的に投資することで、企業価値の向上を目指す「健康経営」の考え方に基づいています。
詳細な認定要件は、毎年更新される申請ガイドで確認することが重要です。
ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)
健康経営優良法人認定取得までのステップ
健康経営優良法人認定は、企業が従業員の健康を重要な経営資源と捉え、戦略的に健康増進に取り組んでいることを示す証です。
この認定を取得するためには、計画的な準備と継続的な取り組みが不可欠となります。
ここでは、認定取得に向けた具体的なステップを解説します。
認定取得に向けた準備と計画
健康経営優良法人認定を目指す上で、最も重要なのが事前の準備と計画です。
認定要件を正確に把握し、自社の健康経営の方向性を明確にすることが成功の鍵となります。
健康経営優良法人認定要件の確認
まず、自社が目指す部門(大規模法人部門または中小規模法人部門)の認定要件を詳細に確認します。
要件は毎年更新される可能性があるため、経済産業省のWEBサイトおよび上記でご紹介したACTION!健康経営のポータルサイトで最新の情報を確認することが極めて重要です。
主な要件には、従業員の健康診断受診率、特定保健指導の実施、ストレスチェックの実施、受動喫煙対策、健康増進施策の実施などが含まれます。
これらの要件を満たすための現状把握と、不足している点への対応計画を立てましょう。
こちらのページでは当社の推進体制や取り組み事例などもご紹介しております。
ライフサポートサービスでの「健康経営」の取り組み事例のご紹介
健康宣言の策定と実践
健康経営優良法人認定において、企業が従業員の健康保持・増進に取り組むことを内外に表明する「健康宣言」の策定は必須です。
この宣言は単なる形式ではなく、経営トップの明確なコミットメントを示すものです。
健康宣言には、企業がどのような健康課題に取り組み、どのような目標を設定するのかを具体的に盛り込みます。
宣言策定後は、その内容に基づいた具体的な健康経営の取り組みを実践し、従業員への周知徹底を図ることが求められます。
たとえば、運動機会の提供、食生活改善の支援、メンタルヘルス対策の強化などが挙げられます。
申請手続きと必要書類
認定要件を満たす準備が整ったら、いよいよ申請手続きに進みます。申請は所定の期間内にオンラインで行われるのが一般的です。
申請には、健康経営の実施状況を示す様々な情報や書類が必要となります。
主な必要書類や提出データは以下の通りです。
健康宣言書
企業が策定した健康宣言の内容
組織体制に関する情報
健康経営を推進する組織体制(担当部署、責任者など)
従業員の健康診断データ
健診受診率、有所見者率などのデータ
特定保健指導の実施状況
対象者数、実施率など
ストレスチェックの実施状況
実施有無、受検率など
健康増進施策の実施状況
実施した健康施策の内容と効果(例:運動イベント、食育セミナー、禁煙支援など)
受動喫煙対策の状況
敷地内禁煙、分煙などの対策状況
その他
労働時間管理、メンタルヘルス対策、ワークライフバランス推進などの取り組み
これらの情報は、申請システムを通じて入力または添付して提出します。
正確かつ網羅的な情報提供が、円滑な審査のために不可欠です。
評価基準と審査のポイント
提出された申請内容は、経済産業省と日本健康会議が定める評価基準に基づき厳正に審査されます。審査のポイントは多岐にわたりますが、特に重視されるのは以下の点です。
経営理念・方針
健康経営が経営戦略として明確に位置づけられているか。
組織体制
健康経営を推進するための責任体制や担当部署が明確か。
制度・施策実行
健康診断の実施、特定保健指導、ストレスチェック、受動喫煙対策など、必須要件を満たしているか。
また、従業員の健康増進に資する具体的な施策が実施されているか。
評価・改善
実施した施策の効果を測定し、継続的な改善サイクルが回っているか。
特に、データに基づいた客観的な取り組み状況や、PDCAサイクルによる継続的な改善努力が評価の重要な要素となります。
大規模法人部門の「ホワイト500」や中小規模法人部門の「ブライト500」といった上位認定を目指す場合は、さらに高いレベルの取り組みと詳細なデータが求められます。
認定後の更新と継続的な取り組み
健康経営優良法人認定は、一度取得すれば永続するものではありません。
認定は毎年更新が必要であり、継続的な健康経営の取り組みが求められます。
更新申請では、前年度の取り組みの継続性や、新たな施策の導入、改善点が評価されます。
認定取得はゴールではなく、むしろ健康経営をさらに推進するためのスタート地点と捉えるべきです。
従業員の健康課題は常に変化するため、企業は健康経営の取り組みを継続的に見直し、改善していく必要があります。認定の更新を通じて、より質の高い健康経営を目指し、企業価値の向上につなげていくことが期待されます。
まとめ
健康経営優良法人認定は、単に企業の健康への取り組みが評価されるだけでなく、持続可能な企業成長を実現するための重要な戦略です。
本記事で解説したように、企業イメージの向上、優秀な人材の確保と定着、従業員の生産性向上、さらには資金調達や優遇措置の可能性など、多岐にわたるメリットを享受できます。
経済産業省が推進するこの制度は、現代社会において企業が社会的な責任を果たしつつ、競争力を高めるための有効な手段と言えるでしょう。
認定取得は、企業の未来への確かな投資であり、積極的に検討する価値があります。