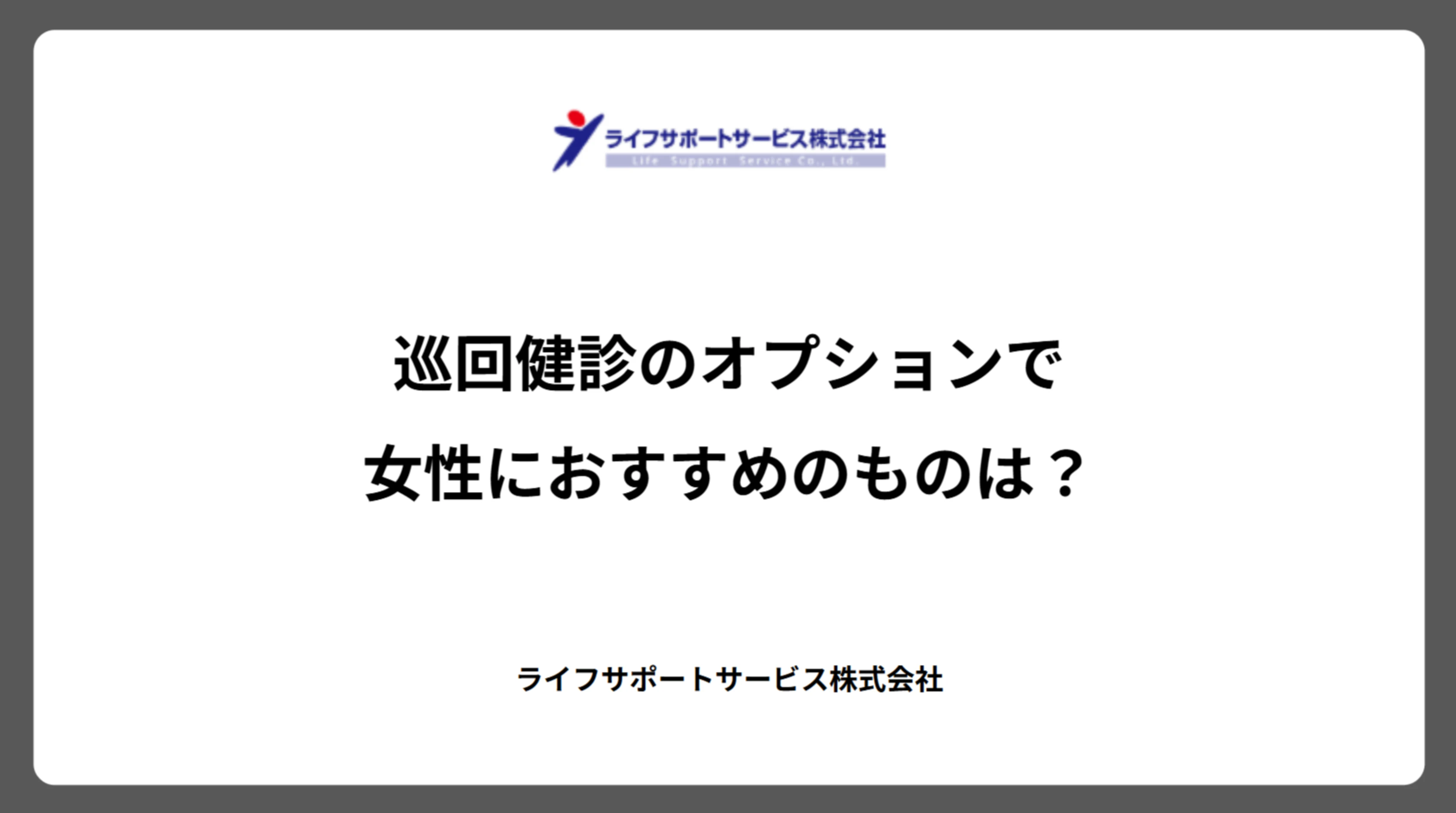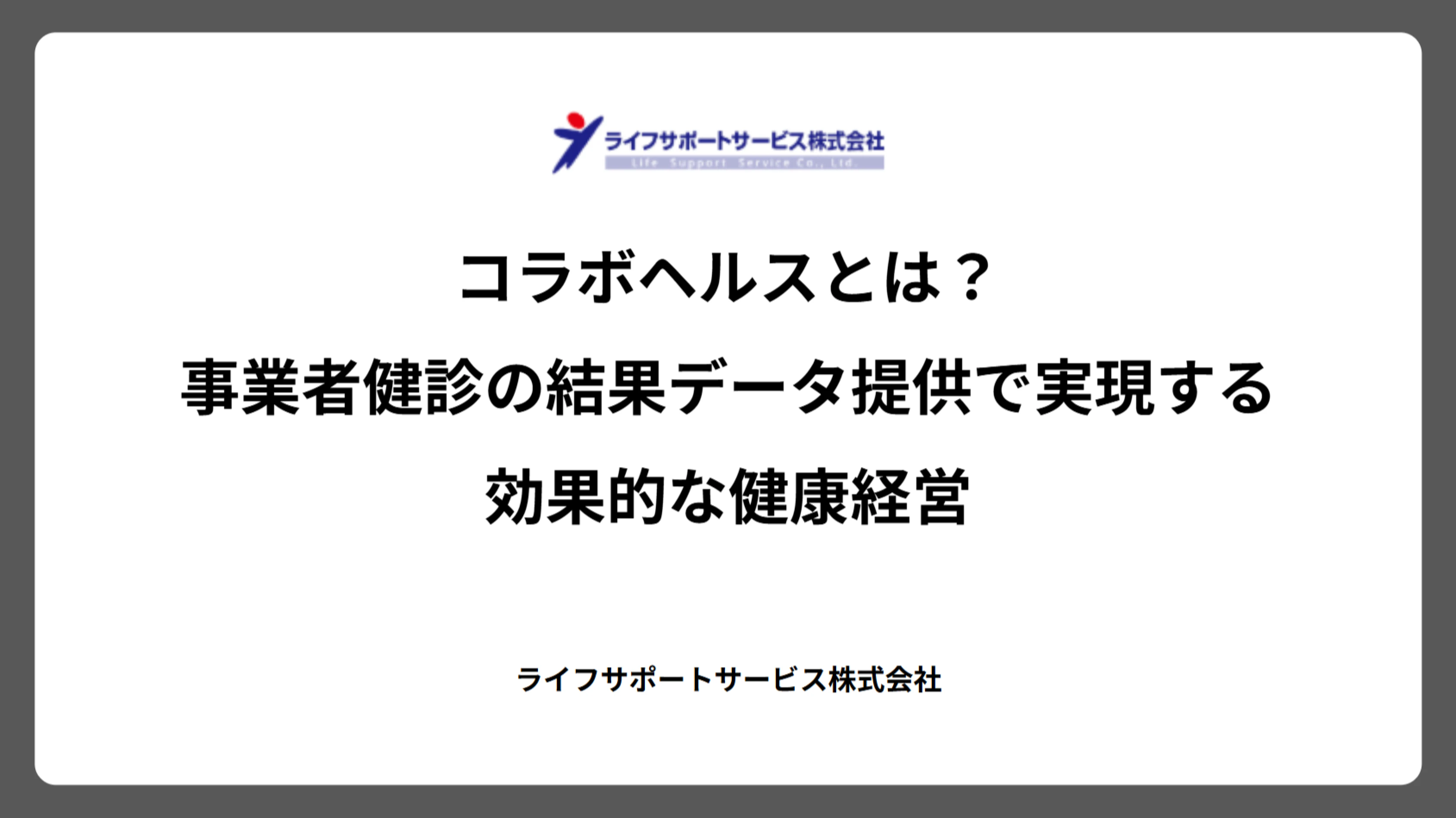記事公開日
健康経営とは?企業が取り組むべき背景と導入メリット、推進ステップを解説!
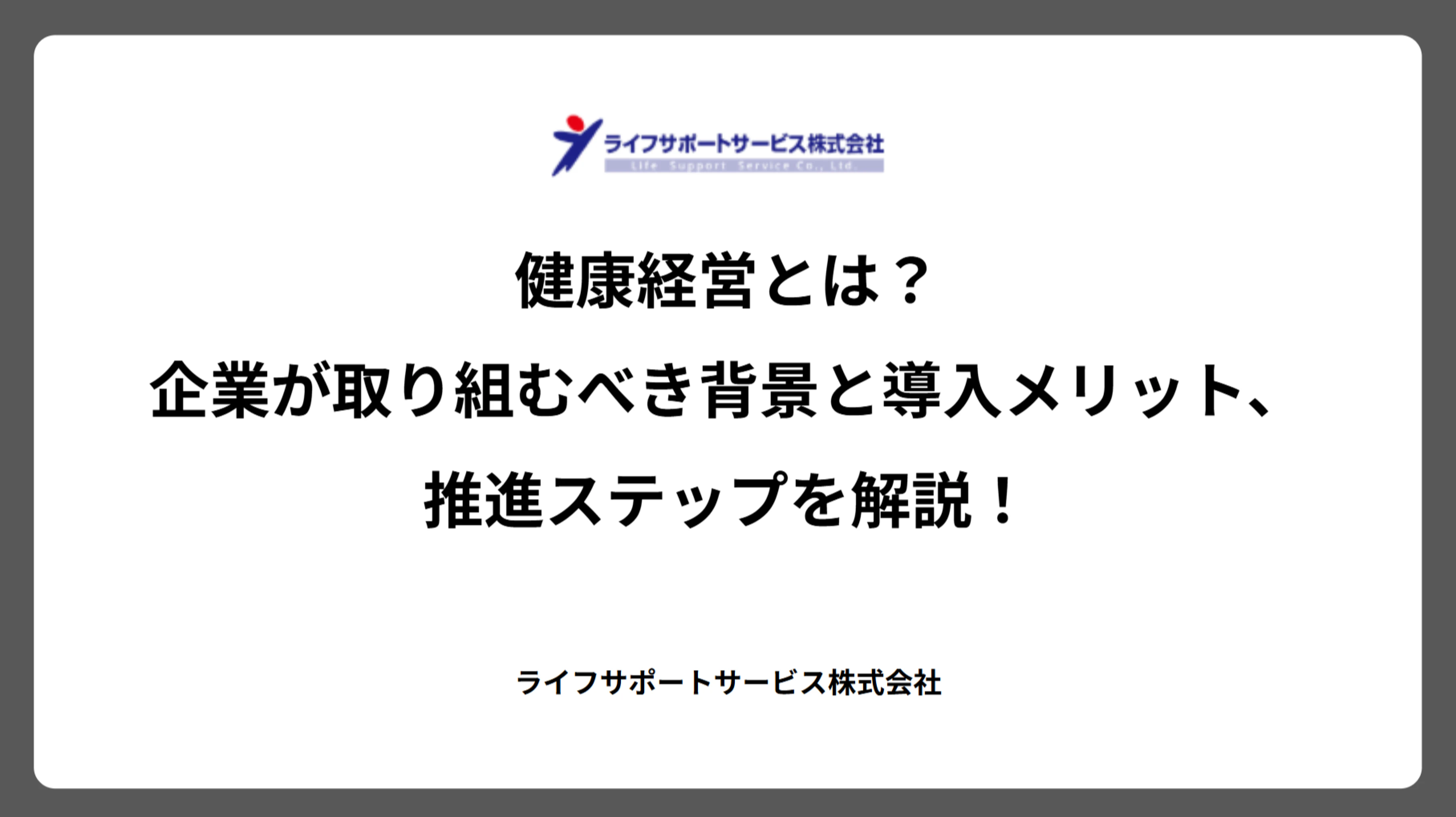
近年、「健康経営」という言葉を耳にする機会が増えましたが、「具体的に何を指すのだろう?」「なぜ自社で取り組む必要があるのか?」と疑問に感じている総務部の健康管理ご担当者様も多いのではないでしょうか。
「健康経営」とは、従業員の健康を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉え、戦略的に健康増進に取り組む経営手法です。
これは、少子高齢化による労働人口の減少、医療費の増大、働き方改革の推進といった社会的背景からも、企業経営において避けて通れないテーマとなりつつあります。
しかし、導入のメリットは従業員個人の健康維持に留まりません。
企業イメージの向上、優秀な人材の確保・定着、そして何より生産性の向上といった、企業価値を高める大きな効果が期待できます。
この記事では、総務部の健康管理担当者様が「健康経営とは何か」を深く理解し、スムーズに導入・推進できるよう、その定義や社会的背景から、具体的な導入メリット、そして実践的な推進ステップまでを徹底的に解説します。
【関連記事】
健康経営優良法人とは?企業が知るべきメリットと認定取得のすべて
- 健康経営とは?
- 健康経営が企業にもたらす5つのメリット
- 優秀な「人材の定着率」と「採用力」の向上
- 従業員の健康改善による「生産性」と「企業活力」の向上
- 企業イメージ・ブランド価値の向上と投資家からの評価(IR)
- リスクマネジメントと医療費の適正化
- 認定制度による優遇措置(健康経営優良法人、健康経営銘柄など)
- 健康経営を導入するステップ
- ステップ1:経営トップの理解と「健康宣言」の策定
- ステップ2:推進体制の構築と担当部門(総務部など)の役割
- ステップ3:現状把握と課題分析(健康診断データ、ストレスチェック、サーベイなど)
- ステップ4:具体的な施策の実行と費用対効果(ROI)の測定
- ステップ5:PDCAサイクルの実践と継続的な改善
- まとめ
健康経営とは?
健康経営とは、企業が従業員の健康管理を単なる福利厚生やリスク回避として捉えるのではなく、経営戦略の一つとして位置づけ、積極的に投資し、推進していく考え方です 。
この概念は、アメリカの心理学者ロバート・ローゼンが提唱した「ヘルシー・カンパニー」という考え方を元に、日本国内では1990年代後半から広まり始め、特に2010年代に入り、経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」の創設などにより、急速に浸透しました 。
具体的な取り組みとしては、従業員の定期健康診断の受診率向上、メンタルヘルス対策、運動機会の提供、食生活改善のサポートなどが含まれます。
重要なのは、これらをPDCAサイクルに組み込み、継続的に改善していくことです。
健康経営が求められる背景
企業が健康経営に取り組む必要性が高まっている背景には、主に以下の3つの要因が挙げられます。
労働人口の減少と人材確保の難化
少子高齢化により働き手が減少する中、企業にとって優秀な人材の確保と定着は最優先課題です。
従業員が長く健康的に働ける環境は、採用市場における大きな差別化要因となります。
医療費の増大と生産性の損失
国民医療費は年々増加しており、企業が負担する健康保険料も上昇傾向にあります。
また、病気や不調が原因で生産性が低下する「プレゼンティーイズム」による経済的損失も無視できない規模になっており、健康への投資が求められています。
働き方改革と企業の社会的責任(CSR)
長時間労働の是正やハラスメント防止など、労働環境への関心が高まる中、従業員の健康を積極的に守ることは、企業の社会的責任として重要視されています。
健康経営が企業にもたらす5つのメリット
健康経営は、従業員だけでなく企業全体に大きなメリットをもたらします。
総務担当者様が経営層へ提案する際に特に強調したい5つのメリットを解説します。
優秀な「人材の定着率」と「採用力」の向上
健康経営に取り組む企業は、「従業員を大切にする会社」として社会的に評価されます。その結果、以下のような効果が期待できます。
離職率の低下
健康的な職場環境は従業員の満足度とエンゲージメントを高め、離職率の低下につながります 。
採用力の強化
就職・転職活動において、企業の健康への取り組みが重視される傾向にあります。
「健康経営優良法人」などの認定は、特に若手や優秀な人材に対する強力なアピールポイントとなります。
従業員の健康改善による「生産性」と「企業活力」の向上
健康経営の最大の効果の一つは、従業員のパフォーマンス向上です。
プレゼンティーイズムの改善
従業員の体調が改善することで、集中力やモチベーションが向上し、出勤していても効率が上がらない状態(プレゼンティーイズム)による生産性の損失を低減できます。
アブセンティーイズムの減少
病欠や休職(アブセンティーイズム)が減少することで、業務の停滞を防ぎ、組織全体の安定した企業活力を維持できます。
企業イメージ・ブランド価値の向上と投資家からの評価(IR)
健康経営は、企業の非財務情報として注目されています。
企業イメージ向上
健康への配慮は、コンプライアンスやガバナンスと並ぶ重要な企業倫理と見なされ、顧客や取引先からの信頼度を高めます。
投資家からの評価(IR)
人的資本への投資として、健康経営はESG投資(環境・社会・ガバナンス)の観点から評価され、企業価値の向上につながります。
リスクマネジメントと医療費の適正化
従業員の健康状態を把握し、対策を講じることは、企業が抱えるリスクを軽減します。
リスクマネジメントの強化
過重労働による労災やメンタルヘルス不調による休職・訴訟リスクを未然に防ぎ、企業経営の安定に貢献します。
医療費の適正化
予防的な取り組みによって従業員の健康状態が改善すれば、長期的に健康保険組合の医療費負担が軽減されます。
認定制度による優遇措置(健康経営優良法人、健康経営銘柄など)
経済産業省が推進する認定制度は、企業の取り組みを評価し、さまざまな優遇措置につなげます 。
健康経営優良法人認定制度
大規模法人向けと中小規模法人向けがあり、それぞれの上位500法人にホワイト500(大規模法人)、ブライト500(中小規模法人)の認定が付与されます。認定を取得することで公共調達や金融機関の融資などで優遇を受けられる場合があります。
健康経営銘柄
東京証券取引所上場企業の中から、特に優れた取り組みを行う企業が選定され、投資家へのアピールが可能になります。
健康経営を導入するステップ
健康経営を単なる一過性のイベントで終わらせず、持続可能な経営戦略として機能させるためには、以下の5つのステップで進めることが重要です。
ステップ1:経営トップの理解と「健康宣言」の策定
【担当部署:経営層、総務部】
健康経営は、現場部門の施策ではなく、経営戦略です。
まずは、経営トップが健康経営の意義と重要性を理解し、コミットメントを示すことが不可欠です。
経営トップへの説明
健康への投資がコスト削減ではなく、将来の利益につながることをデータや事例を用いて説明します。
健康宣言の策定と公表
企業として健康経営に取り組む意思を社内外に明確に示す「健康宣言」を策定し、企業ホームページや社内掲示板で公表します 。
ステップ2:推進体制の構築と担当部門(総務部など)の役割
【担当部署:総務部、人事部、産業医・保健師】
施策を実行・管理するための組織体制を整えます。
担当部門の明確化
総務部や人事部が中心となり、経営層、産業医・保健師、現場の管理監督者などと連携する推進体制(プロジェクトチーム)を構築します。
中小企業では産業医や保健師などの人材を独自で採用するのは難しいので、嘱託や外部サービスの利用も有効です。
予算とリソースの確保
施策に必要な予算を確保し、担当者の業務負担を考慮してリソースを配分します。
ステップ3:現状把握と課題分析(健康診断データ、ストレスチェック、サーベイなど)
【担当部署:総務部、産業医・保健師】
具体的な施策を決定する前に、自社の健康課題をデータに基づいて正確に把握します。
データの収集と分析
健康診断の結果、ストレスチェックの結果、残業時間データ、従業員アンケート(サーベイ)などを集計・分析し、改善が必要な重点課題を特定します。
健康リスクの特定
運動不足、生活習慣病予備群の多さ、高ストレス者の割合など、具体的なリスクを把握します。
ステップ4:具体的な施策の実行と費用対効果(ROI)の測定
【担当部署:総務部、各部門】
ステップ3で特定した課題に対し、具体的な施策を実行します。
同時に、その効果を検証できるよう、測定指標(KPI)を設定します。
施策の実行
喫煙率の低減プログラム、メンタルヘルス研修、特定保健指導、ウォーキングイベントなど、課題に応じた施策を実施します。
費用対効果(ROI)の測定
施策にかかった費用に対し、プレゼンティーイズムの改善による経済効果や医療費の削減効果など、経営効果を可視化します。
ステップ5:PDCAサイクルの実践と継続的な改善
【担当部署:総務部、推進体制全体】
施策は一度実行して終わりではありません。
PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し、継続的に改善していきます 。
- 評価(Check): ステップ4で設定したKPIに基づき、施策の効果を客観的に評価します。
- 改善(Action): 評価結果をもとに、次の年度の施策内容や体制を見直します。
まとめ
健康経営は、従業員の健康を「未来への投資」と捉え、企業価値を高めるための重要な経営戦略です。
まずは経営トップのコミットメントを得て「健康宣言」を行い、社内外に意思を明確に示すこと。
次に、データに基づいて自社の課題を正確に把握し、効果的な施策を実行すること。
この2点が、健康経営を成功させるための鍵となります。
企業の持続的な成長のため、本記事で解説したロードマップを参考に、ぜひ健康経営の推進に着手してください。