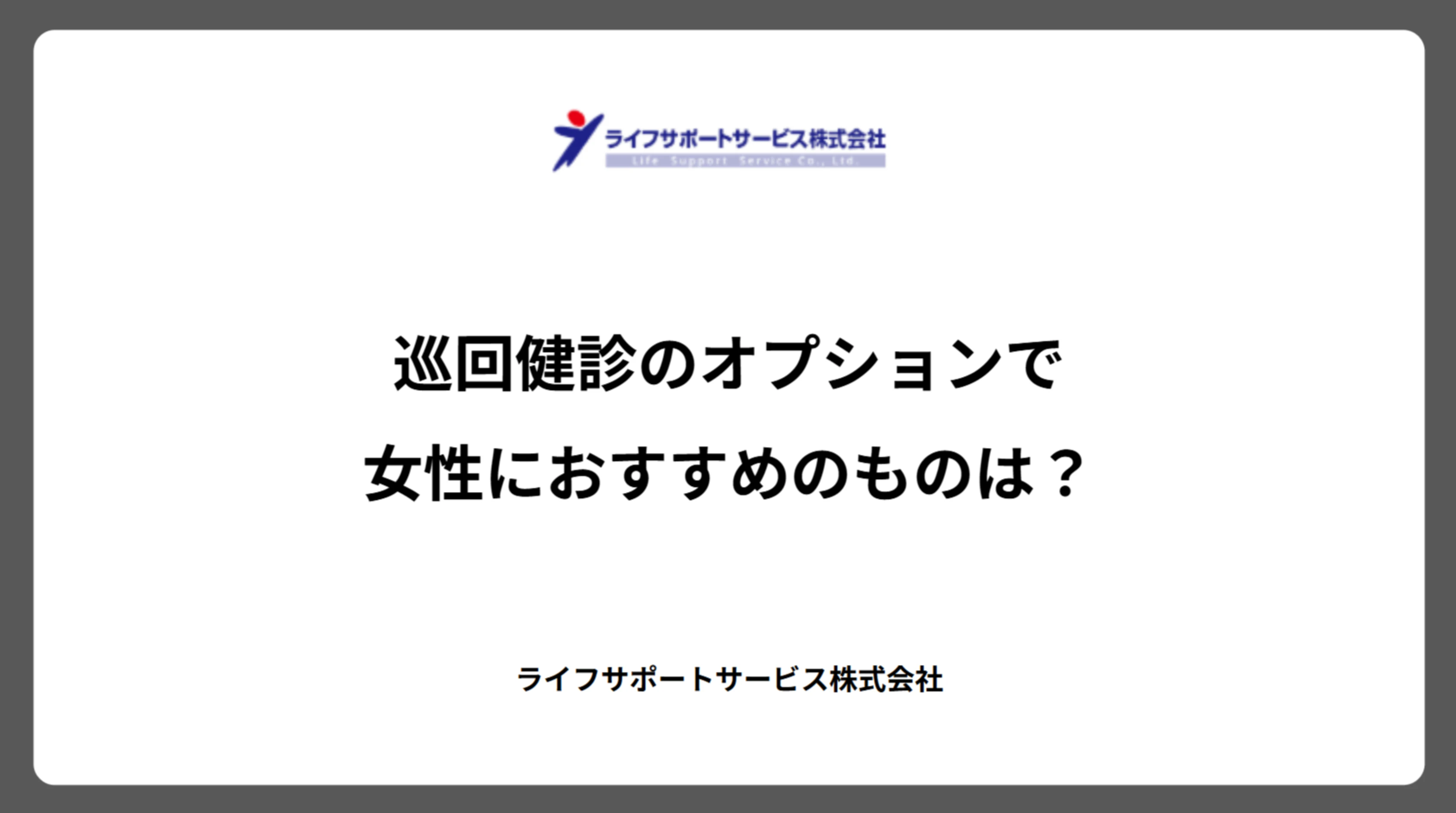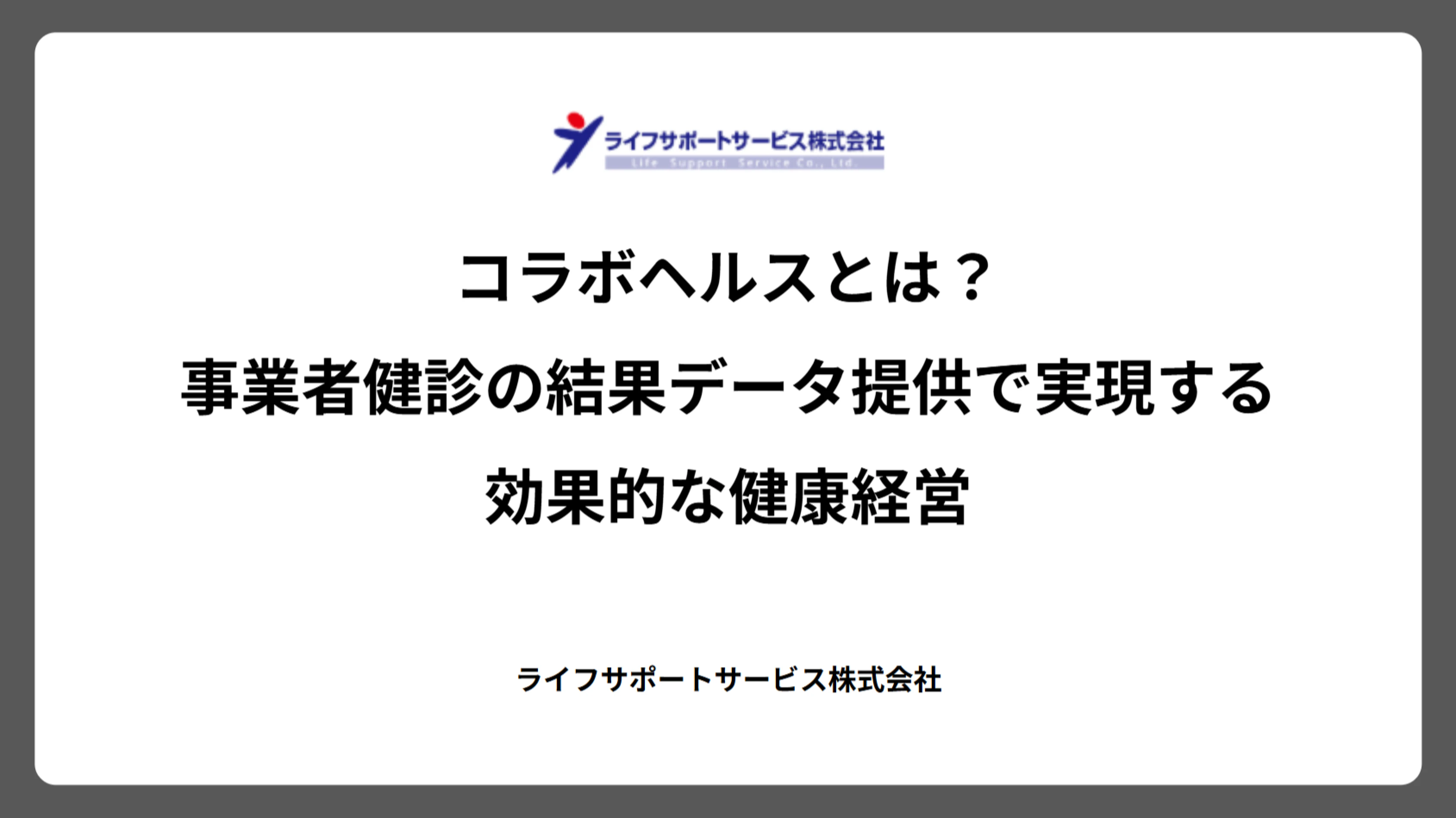記事公開日
中小企業の人事総務担当者必見!ストレスチェック実施の完全ガイド ~準備から職場環境改善への活用まで~

従業員のメンタルヘルス対策、どこから手をつければよいかお悩みではありませんか?
2015年から50人以上の事業場で義務化された「ストレスチェック制度」。中小企業の人事総務ご担当者様にとっては、「名前は知っているけれど、具体的に何をすれば…」「ウチは50人未満だから関係ない?」といった疑問や、日々の業務に追われて後回しになっているケースもあるかもしれません。
しかし、ストレスチェックは単なる「義務」ではなく、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場環境をつくることで、企業の生産性向上や離職率低下につなげるための重要な取り組みです。
本記事では、中小企業の人事総務担当者様に向けて、ストレスチェックを実施するうえで押さえておくべき「ヒト・モノ・コト」のポイントを、準備から実施後の活用まで分かりやすく解説します。
1. ストレスチェック実施に必要な「体制(ヒト)」
まず、ストレスチェックを実施するには、適切な役割分担が必要です。特に個人情報を扱うため、法令で定められた要件を遵守しなくてはなりません。
実施者
-
ストレスチェックの中心的な役割を担い、高ストレス者の選定などを行います。
-
なれる人: 医師(産業医が望ましい)、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師など。
実施事務従事者
-
実施者の補助として、調査票の回収・集計、結果通知の発送(封入作業)など、個人の結果データに触れる可能性のある事務作業を担当します。
-
資格要件: 特になし。
-
⚠️最重要注意点: 人事権(解雇、昇進、異動など)を持つ人(例:経営者、人事部長、直属の上司)は、実施事務従事者になることができません。 これは、結果の不適切な利用による不利益な取り扱いを防ぐためです。
<中小企業の視点>
社内に産業医がいない、または人事権を持たない適任者(例:総務部の他担当者、産業保健スタッフ)を確保するのが難しい場合、ストレスチェックの実施全体(実施者・事務従事者を含む)を外部機関に委託するのが一般的かつ安全な選択肢となります。
2. 【必須】社内への事前通知(周知事項)
ストレスチェックを実施する際は、従業員が安心して受検できるよう、事前に以下の事項を社内規程として定め、全従業員に明確に周知する必要があります。
実施の目的
「メンタルヘルス不調の予防」「職場環境の改善」のためであることを明記します。
実施体制
誰が「実施者」で、誰が「実施事務従事者」なのかを明確にします。
実施期間・方法
いつからいつまで、Web回答か紙の調査票か、などを伝えます。
対象者
常時使用する労働者(パート・アルバイトも要件を満たせば対象)。
結果の取り扱い(プライバシー保護)
-
結果は実施者から直接本人にのみ通知され、本人の同意なしに会社(人事担当者や上司)が個人の結果を見ることは絶対にないこと。
-
結果は厳重に管理・保存されること。
高ストレス者への対応
高ストレスと判定された場合、医師による面接指導を受けられること(申出は任意)、その申出窓口。
不利益な取り扱いの禁止
-
検しなかったこと
-
結果を会社に提供することに同意しなかったこと
-
高ストレス者として面接指導を申し出たこと
-
これらを理由に、解雇、異動、評価の引き下げなどの不利益な取り扱いは一切行わないことを宣言します。
従業員の不安を取り除き、正直に回答してもらうためにも、特に「プライバシー保護」と「不利益な取り扱いの禁止」は強く周知することが重要です。
3. 経営陣が理解しておくべき最重要事項
ストレスチェックを形式的なものに終わらせず、実効性のある取り組みにするためには、経営陣の正しい理解とコミットメントが不可欠です。人事総務担当者として、以下の点を経営陣に説明し、共通認識を持っておきましょう。
「不利益な取り扱いの禁止」と「守秘義務」の徹底
-
前述の「不利益な取り扱いの禁止」は、法律で定められた企業の義務です。これが守られないと、従業員は安心して受検できず、制度自体が機能不全に陥ります。
-
また、ストレスチェックで知り得た個人の健康情報に関する守秘義務違反は、刑罰の対象にもなり得ます。経営陣自らがこの重要性を理解し、社内に厳守させる姿勢を示す必要があります。
目的は「職場環境の改善」にあること
ストレスチェックの真の目的は、「高ストレス者を見つけること」だけではありません。個人の結果を集計・分析した「集団分析」の結果を用いて、部署や職場ごとのストレス要因(例:仕事の量、上司のサポート、人間関係)を特定し、職場環境そのものを改善すること(一次予防)が最も重要です。
「投資」としての認識
ストレスチェックの実施や、その後の職場環境改善にはコストがかかります。しかし、これを「コスト」ではなく、従業員が健康でいきいきと働ける環境を整え、生産性の向上や離職率の低下につなげるための「未来への投資」と捉える視点が求められます。
4. 外部委託先の選び方(中小企業のための選定基準)
社内リソースでの実施が難しい中小企業にとって、外部委託は現実的な選択肢です。しかし、多くの業者がいる中でどこを選べばよいのでしょうか。以下の基準で比較検討することをおすすめします。
| 選定基準 | チェックポイント |
| 1. 実施体制と信頼性 | * 実施者(医師・保健師等)や事務従事者の体制が整っているか。 |
| * 自社の産業医(もし契約していれば)とスムーズに連携できるか。 | |
| * 同規模・同業種の企業での実績は十分か。 | |
| 2. サービス内容 | * 集団分析の質: 単なる結果レポートだけでなく、課題の指摘や具体的な改善提案までしてくれるか。分析結果の報告会や研修を実施してくれるか。 |
| * 実施方法: Web受検、紙受検の両方に対応できるか。多言語対応は可能か。 | |
| * アフターフォロー: 高ストレス者への面接指導(医師の紹介・実施)までワンストップで対応可能か。 | |
| 3. セキュリティ体制 | * 個人情報を適切に管理する体制があるか(「Pマーク(プライバシーマーク)」取得の有無は一つの目安)。 |
| 4. 費用対効果 | * 基本料金にどこまでのサービス(集団分析、面接指導医の紹介など)が含まれているか。オプション料金は明確か。 |
| * 複数の業者を比較し、自社のニーズと予算に合っているか。 |
特に重要なのは「集団分析の質」と「アフターフォロー」です。実施して終わり、ではなく、その後の職場環境改善まで伴走してくれるパートナーを選びましょう。
5. 「やって終わり」にしない!実施後の活用法
ストレスチェックは、実施後の「集団分析」と「職場環境改善」が本番です。
集団分析の実施
-
個人の結果を集計し、部署ごと、職種ごと、年齢層ごとなどでストレス傾向を分析します(※個人が特定されないよう、10人未満の集団での分析は非推奨)。
-
「仕事の量的負担」が高い、「上司のサポート」が低いなど、職場ごとの課題を可視化します。
職場環境改善のアクション
-
集団分析の結果を(個人が特定されない形で)管理職と共有します。
-
課題となっている点について、管理職研修を実施したり、部署ミーティングで話し合ったりする場を設けます。
-
(例)業務プロセスを見直して特定の個人の負担を減らす、コミュニケーション活性化のために定期的な1on1ミーティングを導入する、など。
-
大きな予算をかけなくても、「会議の進め方を変える」「感謝を伝える文化をつくる」など、小さな改善から始めることが可能です。
6. 【補足】50人未満の事業場はどうなる?
本コラム執筆時点(2025年10月)では、常時使用する労働者が50人未満の事業場は、ストレスチェックの実施は「努力義務」とされています。
しかし、働く人のメンタルヘルス対策の重要性は企業規模にかかわらず同じです。また、労働安全衛生法の改正(2025年5月可決・成立)により、3年以内には50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されることが決定されています(施行日は「公布日(2025年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。)。
義務化されるのを待つのではなく、従業員の健康を守り、働きやすい職場づくりの一環として、早めに導入を検討することをおすすめします。
まとめ
ストレスチェックは、適切に準備・運用することで、中小企業の経営課題である「人材の確保・定着」や「生産性の向上」にも貢献する強力なツールとなります。
人事総務ご担当者様は、制度の「守りの側面(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)」を徹底しつつ、「攻めの側面(職場環境改善、生産性向上)」を経営陣や従業員に伝え、ぜひ実りある取り組みにしてください。
本コラムが、貴社のストレスチェック導入・運用の一助となれば幸いです。