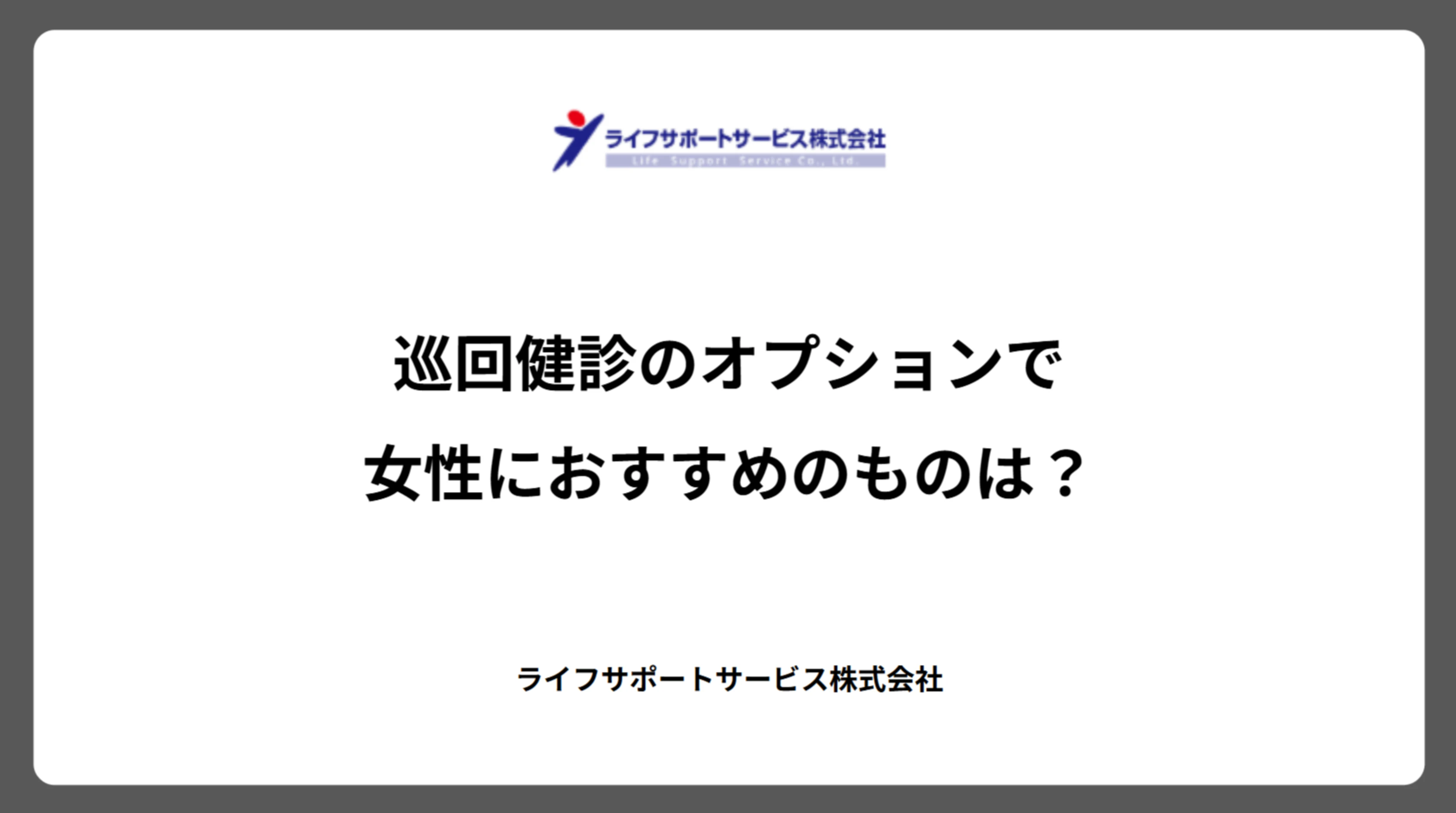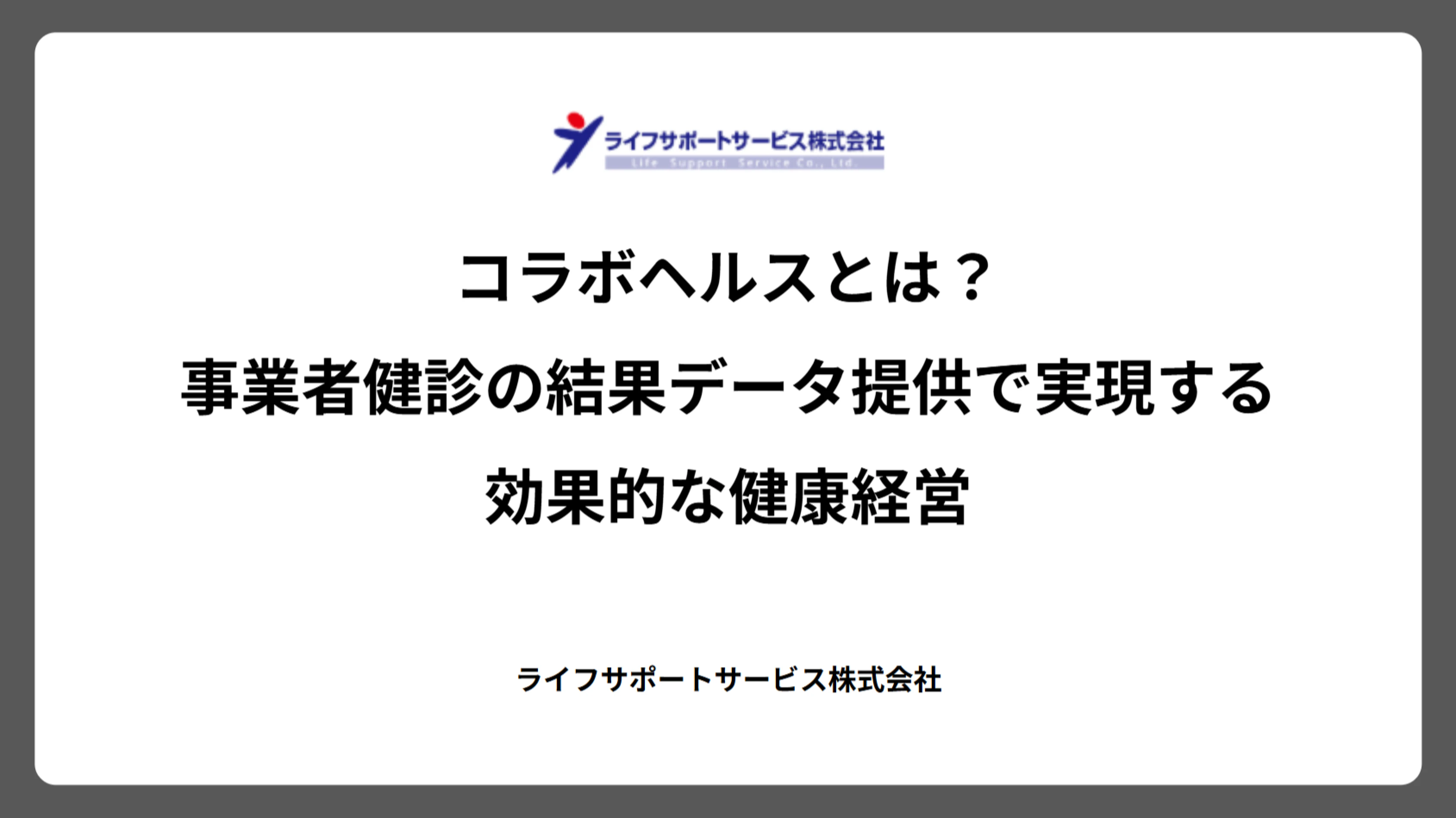記事公開日
最終更新日
労働安全衛生法とは?2024年の改正や企業が知るべきポイントを解説

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を実現するために制定された法律で、「安衛法」や「労安法」などの通称で呼ばれることもあります。
近年、職場の安全対策やメンタルヘルスへの関心が高まり、企業にはより一層の対応が求められています。
特に2024年の改正では、化学物質管理の強化や保護具着用管理責任者の選任義務など、新たな規制が追加されました。
この法律を遵守することで、企業は労働災害を防ぐだけでなく、生産性の向上や従業員のモチベーション向上といったメリットも享受できます。
本記事では、労働安全衛生法の基本から2024年の改正内容、事業者の義務や遵守のメリットまで詳しく解説します。
労働安全衛生法とは
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を防止することを目的とした法律です。
1972年に制定され、以降、時代の変化に応じて度々改正が行われてきました。
職場の安全対策や労働者の健康管理を法律で義務付けることで、企業が責任を持って労働環境を整備し、労働災害のリスクを最小限に抑えることが求められています。
労働安全衛生法は、日本国内の企業や公共団体全般を対象に適用され、業種を問わず、全ての事業者が遵守すべき基本的な労働法の一つです。
特に、総務部の健康管理担当者は、この法律の最新情報を正しく理解し、社内の安全衛生管理体制を整える役割を担っています。
労働安全衛生法の目的と背景
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした法律です。
この法律の目的は大きく3つに分けられます。
労働安全衛生法の目的
労働災害の防止
労働安全衛生法の最も重要な目的は、労働災害の発生を未然に防ぐことです。
職場における事故や健康被害は、労働者にとって深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても業務の停滞や損害賠償などのリスクを伴います。
具体的な防止策として、以下のような施策が法律で義務付けられています。
■リスクアセスメントの実施
職場で発生しうる危険を評価し、適切な対策を講じる。
■安全衛生教育の実施
労働者に対して安全対策や作業手順を周知する研修の実施。
■適切な保護具の支給と着用の徹底
防護メガネや防塵マスクなど、必要な保護具を労働者に提供し、適切に使用するよう指導する。
労働災害を防ぐためには、単に法的な義務を守るだけでなく、企業が積極的に職場の安全対策を推進する姿勢が求められます。
労働者の健康管理と維持
近年、過労やストレスによる健康被害が社会問題となっており、企業には労働者の健康管理を徹底する責務があります。
労働安全衛生法では、健康診断やストレスチェックを実施し、従業員の健康状態を定期的に確認することが義務付けられています。
企業が取り組むべき具体的な健康管理策としては、以下のようなものがあります。
■定期健康診断の実施
企業は年に1回の健康診断を実施し、従業員の健康状態をチェックする義務がある。(有害業務などに従事する従業員については半年に1回の場合もあり)
■ストレスチェックの実施
労働者50人以上の事業所では、メンタルヘルス不調の早期発見を目的に、年に1回のストレスチェックを実施する義務がある。(今後、50人未満の事業所も義務化される見通し)
■巡回健診・健康支援サービスの活用
外部機関と連携して、従業員がスムーズに健康診断を受けられる環境を整える。(巡回健診を活用することで受診率をUPさせる効果があります)
快適な職場環境の形成
労働安全衛生法では、単に「労働災害を防ぐ」だけでなく、労働者が快適に働ける職場環境を整備することも求めています。
快適な職場環境は、労働者のモチベーション向上や生産性の向上に寄与します。
具体的な取り組みとして、以下のような施策が推奨されています。
■適切な温度・湿度管理
労働者が快適に作業できるよう、空調設備の管理を適切に行う。
■作業環境測定の実施
騒音、粉塵、照明の明るさなどを測定し、労働環境を適正に維持する。
■ワーク・ライフ・バランスの推進
残業時間の削減、テレワークの導入など、働きやすい環境づくりを推進。
これらの施策を実施することで、企業は「健康経営」を実現し、従業員の満足度向上にもつながります。
労働安全衛生法の背景
労働安全衛生法が制定された背景には、日本国内における労働環境の問題や、過去の重大な労働災害の発生があります。
労働災害の増加と法整備
日本の産業が発展する中で、工場や建設現場などでの労働災害が多発しました。
特に、1950年代から1960年代にかけては、劣悪な労働環境の影響で多くの労働者が事故に巻き込まれる事例が相次ぎました。
こうした背景を受け、1972年に労働安全衛生法が制定され、企業に対して労働災害防止のための義務が課されるようになりました。
働き方の多様化と健康リスクの増加
近年では、過重労働やストレスによる健康被害が問題視されています。
特に、日本は長時間労働が常態化している企業も多く、過労死やメンタルヘルス不調が社会的課題となっています。
このような状況を改善するため、労働安全衛生法は定期的に改正され、企業に対して労働者の健康管理を強化することが求められるようになりました。
労働安全衛生法と労働基準法との違い
労働関連の法律として「労働安全衛生法」と「労働基準法」の2つがよく取り上げられますが、それぞれの目的や役割は異なります。
企業が適切に法令を遵守するためには、これらの法律の違いを理解し、適用範囲を正しく把握することが重要です。
労働安全衛生法と労働基準法の基本的な違い
| 比較項目 | 労働安全衛生法 | 労働基準法 |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の安全と健康を確保し、職場環境を整備すること | 労働条件の最低基準を定め、労働者の権利を保護すること |
| 主な対象 | 事業者および労働者の健康・安全管理 | 雇用主と労働者の労働契約や賃金、労働時間など |
| 具体的な規定内容 |
|
|
| 罰則の適用 | 事業者が労働者の安全衛生管理を怠った場合に適用 | 企業が労働条件を守らない場合に適用 |
このように、労働安全衛生法は職場の「安全管理・健康管理」に特化した法律であり、労働基準法は労働者の「労働条件や権利保護」に関する法律である点が大きな違いです。
労働安全衛生法の特徴
労働安全衛生法は、企業が安全で快適な労働環境を提供することを目的とし、以下のような項目について具体的なルールを定めています。
労働災害の防止措置
- 事業者は、職場の危険性や有害性を評価(リスクアセスメント)し、必要な防止策を講じる義務がある
- 労働者には、安全に作業を行うための教育を実施する必要がある。
健康診断・ストレスチェックの実施
- 企業は従業員の健康を維持するため、定期健康診断やストレスチェックを義務付けられている。
- 全従業員が受診できるような配慮が求められており、外部機関と連携して巡回健診・健康支援サービスを活用することも有効な手段になる。
管理者の選任義務
- 50人以上の従業員を抱える事業所では、産業医や衛生管理者の選任、衛生委員会の開催が義務付けられている。
- 産業医や衛生管理者の選任人数は、業種・従業員数により異なる。
快適な職場環境の形成
- 労働環境を改善し、労働者が健康的に働けるようにするための基準を定めている。
労働基準法の特徴
一方、労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とし、雇用主が最低限守るべきルールを定めています。主な内容として、以下の点が挙げられます。
労働時間・休日・休暇の規定
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合は、残業手当を支払う必要がある。
労働者には一定の休憩時間や休日を付与する義務がある。
最低賃金の保証
都道府県ごとに定められた最低賃金を下回る賃金を設定することはできない。
解雇のルール
正当な理由なく労働者を解雇することは禁止されている。
30日以上前の解雇予告または解雇手当の支払いが義務付けられている。
労働安全衛生法改正とは?2024年のポイント
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するために定められた法律であり、時代の変化に応じて改正が行われています。
2024年の改正では、特に化学物質の管理強化や保護具着用管理責任者の選任などが義務化され、企業にとって対応が必須となる重要な改正点が含まれています。
ここでは、2024年の労働安全衛生法改正のポイントについて詳しく解説し、企業が対応すべき事項を明確にします。
2024年労働安全衛生法改正の背景
近年、日本国内では労働災害の防止だけでなく、職場環境の改善やメンタルヘルス対策の強化が求められています。
特に、化学物質による健康被害の増加や安全対策の不足が課題とされており、2024年の改正では「化学物質管理の厳格化」「保護具着用管理責任者の選任」「健康管理の強化」といったポイントが追加されました。
改正の主な目的
- 労働者の健康リスクを軽減するための化学物質管理の強化
- 事故防止のための適切な保護具着用の義務化
2024年の改正ポイント
2024年の労働安全衛生法改正の主なポイントは以下の2つです。
化学物質管理の厳格化
近年、工場や研究所などで化学物質による健康被害が問題視されており、2024年の改正では化学物質のリスクアセスメントの実施が義務化されました。
これにより、事業者は以下の対応を求められます。
- 化学物質管理者の選任(特定の業種)
- 使用する化学物質のリスク評価の実施
- 適切な安全対策と作業環境の改善
保護具着用管理責任者の選任
安全対策の一環として、保護具(防塵マスク、ヘルメット、ゴーグルなど)の適切な使用が企業の義務となります。
2024年の改正では、「保護具着用管理責任者」を選任し、適切に保護具が使用されるよう管理することが求められます。
企業が対応すべきポイント
2024年の労働安全衛生法改正に対応するため、企業が取るべき具体的なアクションを以下にまとめました。
- 化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任
- 労働者への安全教育の実施
- 産業医との連携による健康管理体制の強化
労働安全衛生法の改正に適切に対応することで、企業は労働災害の防止、従業員の健康維持、コンプライアンスの強化を実現できます。
まとめ
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るための基本法であり、企業が適切な労働環境を整備するために重要な役割を果たします。
特に、2024年の改正では、化学物質管理の強化、保護具着用管理責任者の選任など、企業が迅速に対応すべきポイントが追加されました。
企業の総務部門や健康管理担当者は、最新の法改正を理解し、労働者の安全確保と健康維持に向けた具体的な対策を講じることが求められます。
労働環境の整備は、企業にとって単なる法令遵守の問題ではなく、従業員の健康と生産性の向上に直結する重要な経営課題です。
企業が労働安全衛生法を適切に守ることで、職場の安全を確保し、従業員の働きやすい環境を提供することができます。
今後も、法改正の動向をチェックし、定期的な見直しを行いながら、労働環境の最適化を図ることが不可欠です。
特に、健康管理に関しては、従業員の健康維持と企業のリスク回避を両立させることが求められ、外部機関との連携や活用が大きなカギになります。
労働安全衛生法の遵守は、企業の信頼性向上と持続可能な経営のために欠かせません。
従業員の安全と健康を守るために、今すぐ適切な対策を講じましょう。