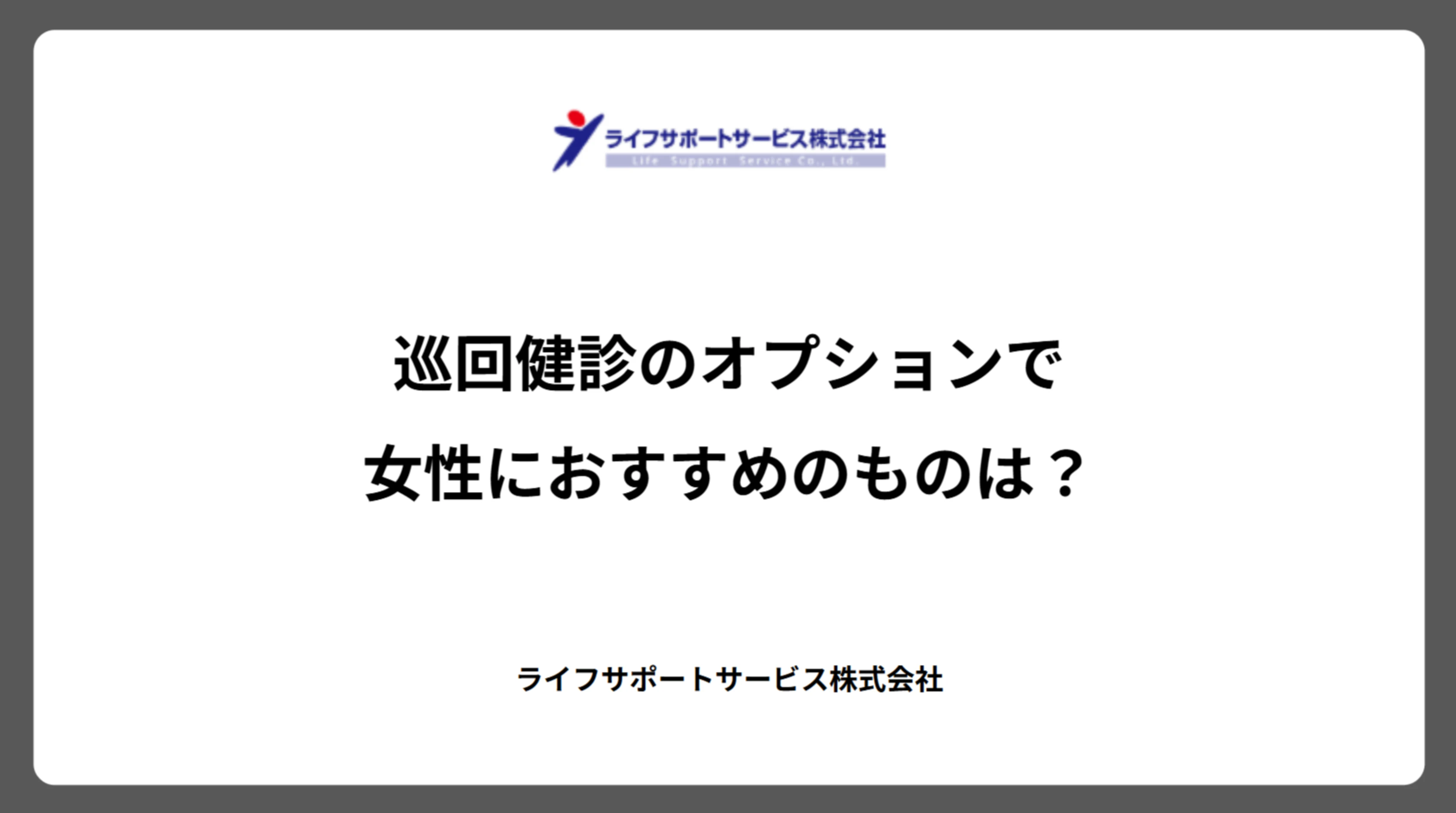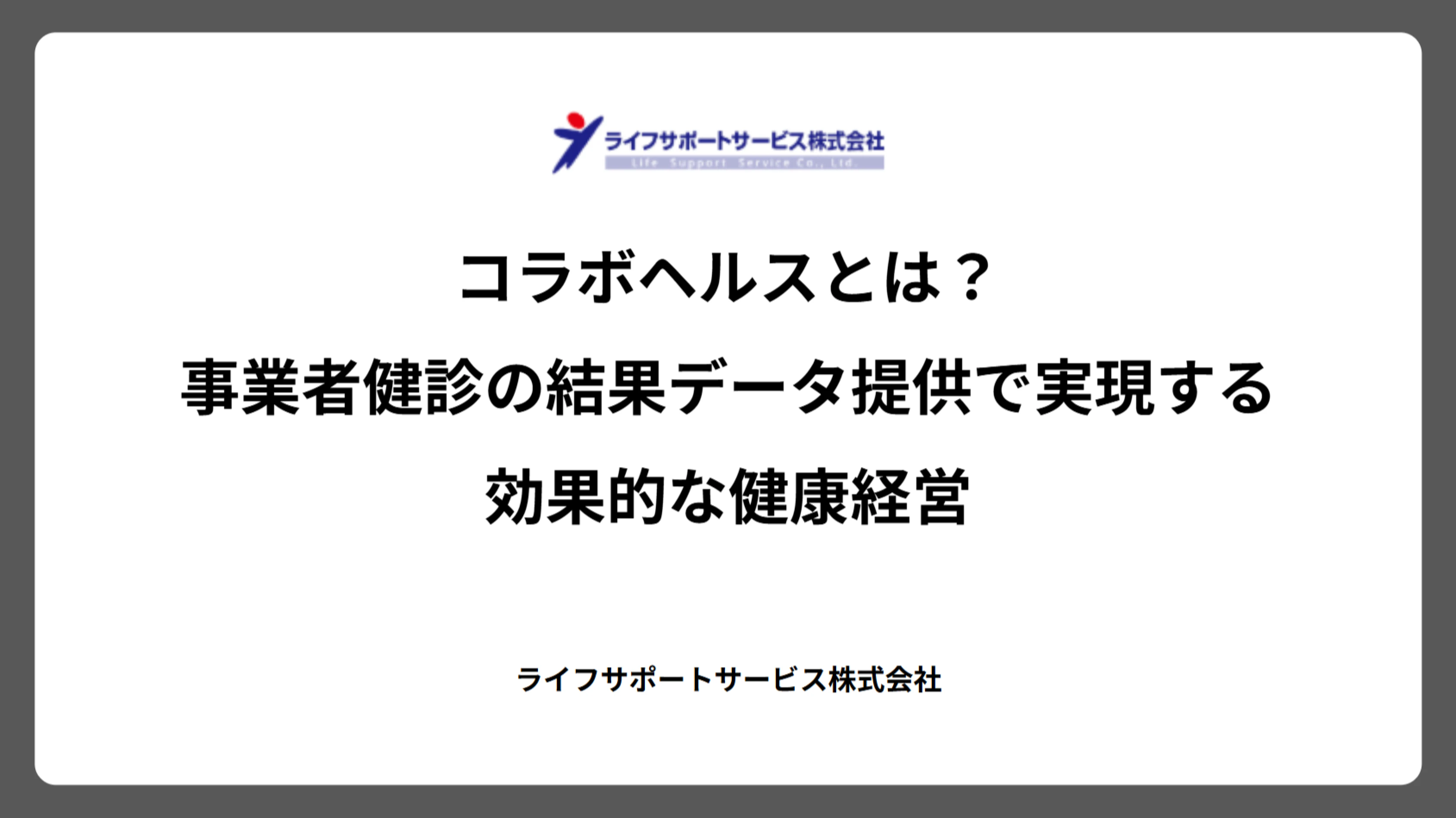記事公開日
最終更新日
協会けんぽ健診とは?費用・対象・メリットまで健康管理担当者向けに解説

企業の健康管理を担う総務部などの担当者にとって、社員の定期健康診断は欠かせない業務の一つです。
なかでも中小企業の多くが利用する「協会けんぽ健診」は、制度の内容やメリットを正しく理解しておくことが大切です。
しかし、「協会けんぽ健診とはそもそも何か?」「対象者や費用負担はどうなっているのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「協会けんぽ健診」の基本的な仕組みから、費用、対象範囲、導入メリットまで、健康管理担当者の視点でわかりやすく整理してご紹介いたします。
協会けんぽ健診とは?
制度の概要
「協会けんぽ健診」とは、正式には「全国健康保険協会(協会けんぽ)による生活習慣病予防健診」のことを指し、協会けんぽに加入している中小企業の被保険者(原則として35歳以上)が対象となる健康診断制度です。
対象者は全国に広がっており、多くの企業において事業者健診(定期健康診断)を兼ねて「協会けんぽ健診」の制度を利用しています。
この健診は、一般健診に加え、一定条件を満たす場合には付加健診や乳がん・子宮頸がん検診などのオプション検査も受けられる仕組みが整えられています。
事業者側からすると、比較的低負担で従業員に必要な健康管理施策を提供できる点が特徴です。
法律上の背景と目的
事業者には労働安全衛生法により、年1回の定期健康診断を実施する義務が課されています。
協会けんぽ健診はその義務を果たす方法のひとつであり、法令遵守の観点でも導入意義が大きいといえます。
また、この制度は単に法的義務を果たすだけでなく、生活習慣病などの早期発見・早期治療を促すことを目的としていて、労働安全衛生法で定められた定期健康診断の項目よりも検査内容が充実しています。
近年では健康経営や働き方改革の一環として、社員の健康増進に積極的に取り組む企業が評価される風潮が強まっており、健診の重要性はさらに増しています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の役割
全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」は、中小企業の従業員やその家族を主な対象とする公的医療保険制度の運営主体です。
厚生労働省の管轄下にあり、全国の中小規模事業所が多く加入しています。
協会けんぽは、健康診断の実施支援に加えて、健診後のフォローアップ(保健指導や健康相談)なども展開しており、事業所と連携しながら被保険者の健康維持をサポートしています。
近年では、巡回健診サービスのように企業の負担を減らす支援サービスも活用され始めており、健康管理体制の外部委託を検討する企業も増加しているようです。
健診の対象者と実施タイミング
対象となる従業員の条件
協会けんぽ健診の対象となるのは、協会けんぽに加入している被保険者のうち、35歳以上の従業員です。
具体的には、正社員を中心とした雇用形態で、健康保険の被保険者として登録されている方が対象となります。
35歳未満の従業員については、協会けんぽ健診の対象外となります。(事業者としては労働安全衛生法で定められた定期健康診断は実施しなければなりません)
なお、扶養家族(被扶養者)はこの健診の対象とはなります。40歳~74歳の被扶養者については「特定健康診査」の対象となりますので、そちらをご検討ください。
※「特定健康診査」とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目してこれらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導を受けていただくことを目的とした健康診査です。
雇用形態別の取り扱い(正社員・パート等)
正社員であれば原則として健康保険に加入していますが、パートタイマーやアルバイト従業員についても、勤務時間や雇用契約の内容によっては協会けんぽに加入しているケースがあり、その場合は35歳以上の方は協会けんぽ健診の対象者となります。
たとえば、週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であるなど、一定の条件を満たす非正規労働者は、健康保険の被保険者として協会けんぽに加入し、健診を受ける資格を得ます。
健康管理担当者としては、個々の雇用契約に基づく保険加入状況を正確に把握することが重要です。
実施時期と頻度
協会けんぽ健診は、年1回の受診が基本となり、年度単位で4月から翌年3月までの間で1回受診できます。
具体的な日程や予約方法は、事業所ごとに異なり、医療機関との契約や巡回健診サービスの導入状況によって調整されます。
補助はある?健診の費用と負担の仕組み
企業・従業員の費用負担の割合
協会けんぽ健診では、健診費用の一部を協会けんぽが補助する制度があり、企業と従業員双方の負担が軽減される仕組みになっています。
基本的な健診である「一般健診」の費用は総額2万円程度ですが、協会けんぽが費用の一部を負担し、企業または従業員が負担する自己負担額は5,282円になります。
費用負担の内訳は企業の方針によって異なります。事業者健診の代用として協会けんぽの健診を実施している企業が多く、その場合は全額を会社で負担する場合がほとんどです。事業者健診の定期健康診断を別に実施していて協会けんぽの健診を従業員が任意で受診するケースなどでは自己負担額を従業員が支払うという場合もあります。
いずれにしても、協会けんぽの補助を活用することで、通常の健康診断に比べて非常に安価に受診が可能となります。
補助の有無と内容
協会けんぽによる補助制度は、対象年齢や健診種別に応じて異なります。
代表的な協会けんぽ健診の対象年齢は以下の通りです。
- 一般健診:35歳以上
- 付加健診:40歳以上の5歳刻み(40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳)
※付加健診単独での受診は不可(一般健診と併せて受診) - 子宮頸がん検診:20歳~74歳の偶数年齢の女性
※40歳以上は子宮頸がん検診単独での受診は不可(一般健診と併せて受診) - 乳がん検診:40歳~74歳の偶数年齢の女性
※40歳代と50歳以上でマンモグラフィ検査の撮影枚数が異なります
※乳がん検診単独での受診は不可(一般健診と併せて受診)
企業としては、こうした補助制度を活用して健診実施を計画することで、年間の福利厚生コストの見通しも立てやすくなります。
自己負担額の目安
協会けんぽの補助が適用された後の自己負担額は、健診種別によって異なりますが、おおよそ以下のような金額が目安となります。
(こちらは2026年3月までの金額です。2026年4月以降は健診体系の見直しが予定されていて、自己負担額も変更になる予定ですのでご注意ください)
- 一般健診:5,282円
- 付加健診:2,689円
- 子宮頸がん検診:970円
- 乳がん検診:40歳~48歳 1,574円、50歳以上 1,013円
企業が定期健康診断を兼ねて協会けんぽ健診を実施すれば、補助制度で費用負担が抑えられ、より充実した健診項目を実施できるので従業員の満足度や受診率向上にもつながります。
協会けんぽ健診の検査項目などはこちらをご確認ください
生活習慣病予防健診のご案内 | 協会けんぽ
協会けんぽ健診のメリット
企業側のメリット
協会けんぽ健診を導入することによる最大のメリットは、法令遵守を効率的に実現できる点にあります。
労働安全衛生法では、年1回の定期健康診断の実施が事業者に義務付けられていますが、協会けんぽの制度を活用することで、その義務をスムーズに果たすことができます。
さらに、協会けんぽによる費用補助があるため、企業のコスト負担を抑えつつ健康管理体制を構築できるという点も見逃せません。
これは、特に中小企業や予算が限られた公共団体にとって大きなメリットです。
また、近年注目される「健康経営」の推進にもつながります。
健診データを活用することで、従業員の健康リスクを早期に把握し、病気の予防や職場環境改善に役立てることができます。
結果として、労働生産性の向上や休職率の低下にもつながり、企業全体の健全な運営に貢献します。
従業員側のメリット
従業員にとっても、協会けんぽ健診の利用は多くのメリットがあります。
まず、補助によって自己負担額が低く抑えられるため、経済的な負担なく定期的な健康チェックを受けることができます。
これにより、健診への心理的ハードルが下がり、受診率の向上が期待されます。
また、協会けんぽ健診は生活習慣病の早期発見・予防を目的としているため、将来的な健康リスクに対する意識を高めるきっかけとなります。
特に40歳代以上の社員にとっては、自身の健康状態を見直す重要な機会となるでしょう。
さらに、企業が「巡回健診・健康支援サービス」のような訪問型健診を導入していれば、従業員はわざわざ医療機関に足を運ぶことなく、職場で手軽に健診を受けることができるため、時間的な負担も軽減されます。
このように、制度とサービスをうまく活用することで、従業員の健康管理がより現実的かつ継続的なものとなっていきます。
巡回健診などの導入でより便利に
「巡回健診・健康支援サービス」の特徴
近年、多くの企業や公共団体で注目されているのが、「巡回健診・健康支援サービス」の導入です。
これは、医療機関のスタッフが企業や施設に訪問し、その場で健診を実施する出張型サービスを指します。
ライフサポートサービスの「巡回健診・健康支援サービス」では、35歳以上の協会けんぽ健診に加え、35歳未満の定期健康診断やオプション検査などにも対応可能です。
さらに、健診結果の一括管理やフォローアップ支援など、健康管理担当者の業務を包括的にサポートするサービスも備えています。
従業員の受診率向上と管理コストの削減を両立させたい企業にとって、非常に実用的なソリューションといえるでしょう。
ライフサポートサービスの巡回健診についてはこちらをご参照ください
巡回健診・集団健診 | ライフサポートサービス株式会社
出張型の巡回健診 活用メリット
出張型の巡回健診には、以下のような多くのメリットがあります。
- 時間的な効率性:従業員が通常業務の合間に健診を受けられるため、業務への支障が最小限で済みます。
- 受診率の向上:移動の手間がなくなることで、健診を受ける心理的・物理的ハードルが下がり、結果として受診率が高まります。
- 多拠点対応が可能:支社や営業所など、複数拠点を抱える企業でも、同様の品質で均一な健診サービスを提供できます。
- リソース削減:予約管理、結果通知、アフターフォローまで一括で委託できるため、総務部門の業務負荷が軽減されます。
こうしたメリットから、巡回健診は単なる利便性の向上にとどまらず、企業全体の健康経営推進に貢献する手段としても注目されています。
予約・申し込みの流れ
巡回健診の導入は、非常にシンプルな流れで進めることができます。
1.問い合わせ・相談
導入を検討している企業は、サービス提供事業者に相談し、健診項目や実施人数、実施場所などを確認します。
2.プラン設計と見積もり
企業の要望に応じて最適な健診プランが提案され、費用とスケジュールが提示されます。
3.日程調整・告知
実施日が決まり次第、社内で従業員に向けた周知・予約受付がスタートします。
オンライン予約に対応しているサービスも増えています。
4.健診当日
実施当日は医師や看護師などの健診スタッフが現地に出向き、健診を実施します。
5.結果配布
受診後2週間~1ヶ月程度で、受診者用の個別の健診結果と事業者の健診結果控えが送付されます。
サービス提供元によっては、オンライン管理ツールの提供や、健康支援アドバイス、リスク判定付きレポートなどのオプションも用意されており、企業の健康管理レベル向上にも寄与します。
ライフサポートサービスでの実施フローはこちらをご参照ください
巡回健診・集団健診 実施フロー | ライフサポートサービス
まとめ
協会けんぽ健診は、全国健康保険協会が提供する制度として、中小企業を中心に広く活用されている健康診断の仕組みです。
法令対応だけでなく、企業・従業員の双方にメリットのある制度として、健康経営の基盤を支える重要な役割を果たしています。
対象となる従業員や費用負担の内訳、補助制度の活用など、基本的な内容を正しく理解しておくことで、健診業務の運用効率が大きく向上します。
また、出張型の「巡回健診・健康支援サービス」などを取り入れれば、より手間なくスムーズに制度を実施でき、社員の受診率向上やコスト管理にも効果的です。
健康管理担当者としては、単に「義務を果たす」ための健診ではなく、社員の健康意識を高め、働きやすい環境づくりに貢献する機会として、制度の活用方法を再検討してみることが推奨されます。
協会けんぽ健診を上手に活用して、自社の健康経営の一歩を踏み出しましょう。
【2025年10月 追記】
2026年度から大幅な変更が予定されています。
詳細がわかりましたら改めてコラムをアップロードしたいと思います。