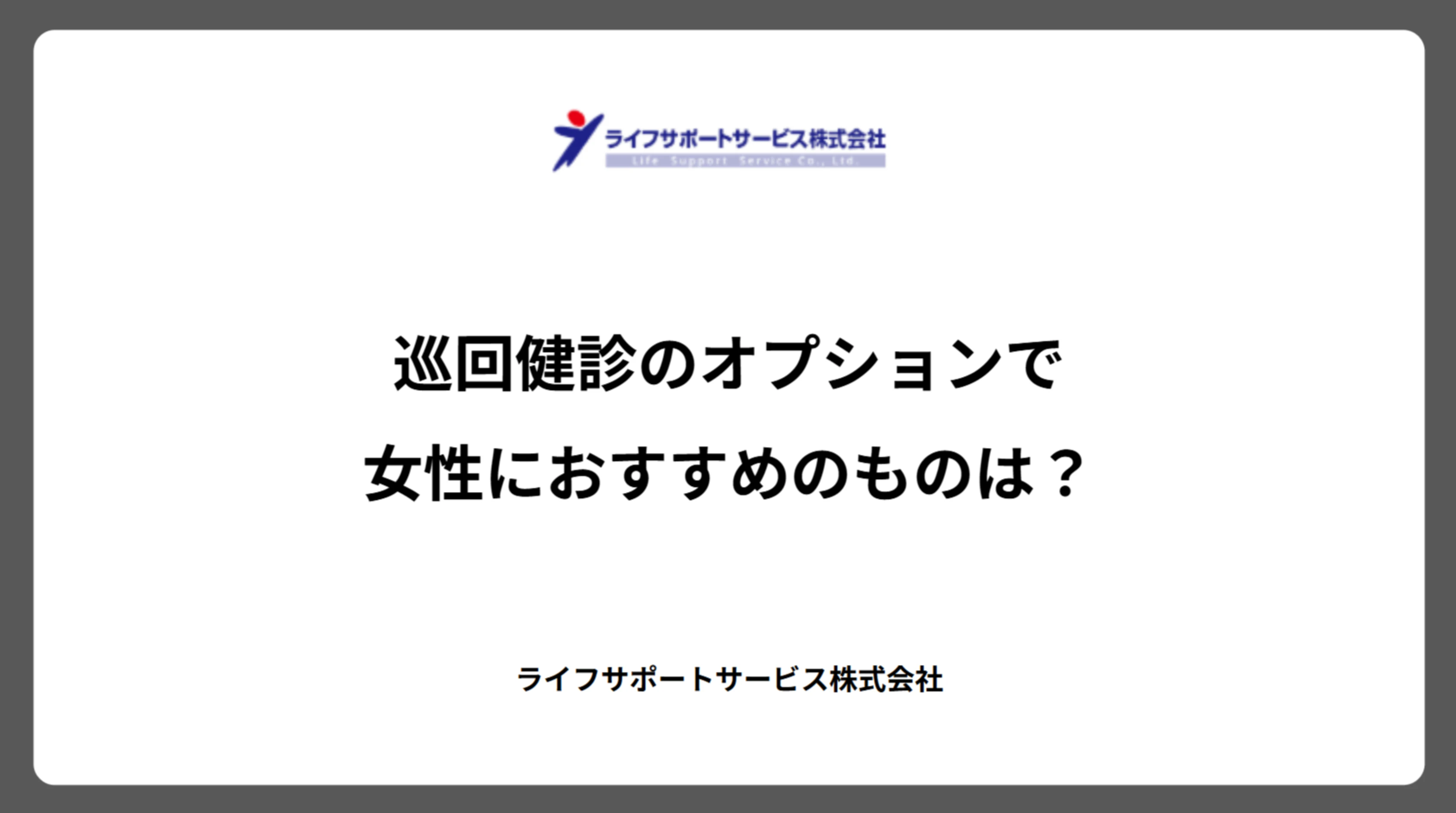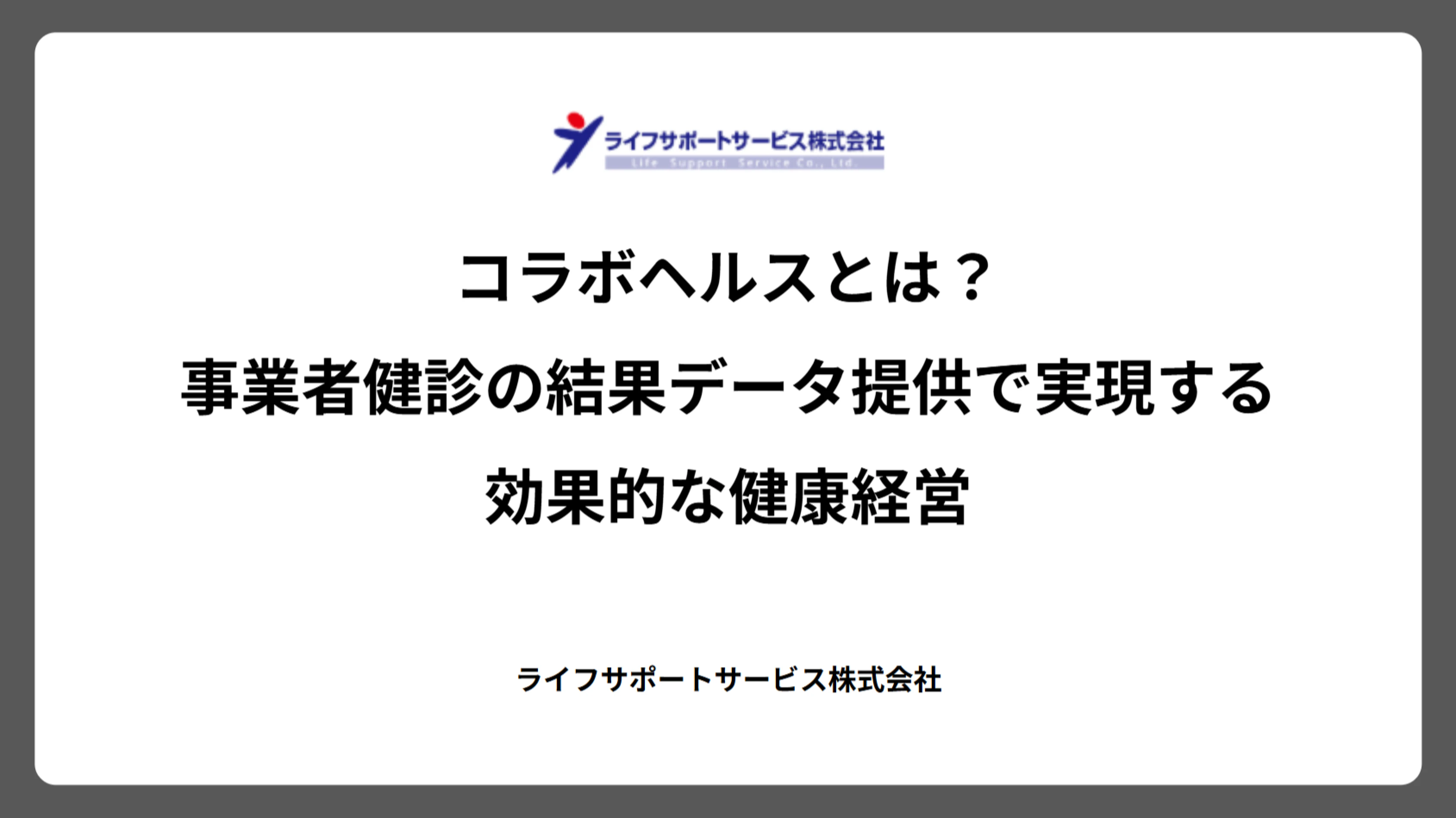記事公開日
最終更新日
職場の健康診断に関する法律:労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条・第44条の重要性

職場の健康診断に関する法律:
労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条・第44条の重要性
労働者の健康は、企業にとって最も重要な経営資源の一つです。健康な労働者があってこそ、企業の持続的な発展は可能となります。日本では、この労働者の健康を守るために「労働安全衛生法」が制定されており、その中でも特に重要な条文として「第66条」が挙げられます。また、その詳細な実施基準を定める「労働安全衛生規則」の「第43条」と「第44条」も、労働者の健康管理において不可欠な規定です。
この記事では、これらの条文が具体的にどのような内容を定めているのか、企業はどのような義務を負うのか、そして労働者にとってどのような意味を持つのかを詳しく解説します。
労働安全衛生法第66条:健康診断の実施義務の基本
労働安全衛生法第66条は、事業者に労働者に対する健康診断の実施を義務付けている、労働者の健康管理の根幹をなす条文です。
【労働安全衛生法第66条(抜粋)】
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
この条文は、事業者が労働者に対して定期的に健康診断を受けさせることを義務付けており、その具体的な内容や実施方法については、厚生労働省令(労働安全衛生規則など)で定めるとされています。
この条文のポイント
- 事業者の義務: 労働者への健康診断の実施は、事業者の法的義務です。
- 対象: 全ての労働者が対象となります。パートタイム労働者なども一定の要件を満たせば対象となります。
- 目的: 労働者の疾病の早期発見、健康状態の把握、疾病の予防、健康増進を図ることが目的です。
- 罰則: 健康診断の実施を怠った場合、事業者は罰則の対象となる可能性があります。
労働安全衛生規則第43条:雇入れ時の健康診断
労働安全衛生規則第43条は、労働者を雇い入れる際に行う健康診断について具体的に定めています。
【労働安全衛生規則第43条(抜粋)】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
七 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン量)
八 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
九 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
十 血糖検査
十一 心電図検査
この条文は、新たに労働者を雇い入れる際に、その労働者の健康状態を把握し、その後の業務に適応できるか、あるいは健康上のリスクがないかを確認することを目的としています。
この条文のポイント
- 対象: 「常時使用する労働者」が対象です。これは、正社員だけでなく、期間の定めのない契約で雇用され、通常の労働時間で勤務するパートタイマーなども含まれます。
- 実施時期: 雇入れ時、つまり入社する前に実施するのが原則です。ただし、入社後速やかに実施することも認められています。
- 検査項目: 上記の通り、詳細な検査項目が定められています。これらの検査を通じて、労働者の基本的な健康状態を把握します。
- 目的: 労働者の健康状態を把握することで、適切な業務への配置や、入社後の健康管理計画の策定に役立てます。
労働安全衛生規則第44条:定期健康診断
労働安全衛生規則第44条は、事業者が毎年1回、定期的に労働者に行う健康診断について定めています。
これは、労働者の健康状態の変化を継続的に把握し、疾病の早期発見や予防に繋げるための最も重要な健康診断です。
【労働安全衛生規則第44条(抜粋)】
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
七 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン量)
八 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
九 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
十 血糖検査
十一 心電図検査
検査項目は、雇入れ時の健康診断とほぼ同じ内容が定められています。
これは、定期的に同じ項目を検査することで、健康状態の変化を比較しやすくする意味もあります。
この条文のポイント
- 対象: 「常時使用する労働者」が対象であり、雇入れ時の健康診断と同様です。
- 実施時期: 「一年以内ごとに一回、定期に」実施することが義務付けられています。毎年同じ時期に実施することが望ましいとされています。
- 目的: 労働者の健康状態を継続的に把握し、生活習慣病の予防や早期発見、業務による健康障害の発生を未然に防ぐことが主な目的です。
- 事後措置: 健康診断の結果、異常が認められた労働者に対しては、医師の意見を聞き、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる必要があります。
なお、今回の記事では第43条(雇入れ時の健康診断)と第44条(定期健康診断)を取り上げていますが、それ以外にも第45条(特定業務従事者や海外派遣労働者の健康診断)、第47条(休職従業員の検便)、第48条(歯科医師による健康診断)なども定められていますので、詳しくは『e-GOV 法令検索』にてご確認ください。
労働者の健康を守るための企業の役割
労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第43条・第44条は、企業が労働者の健康を守る上で果たさなければならない重要な役割を明確にしています。
- 健康診断の確実な実施: 雇入れ時および定期的な健康診断を計画的に実施し、全ての対象労働者が受診できるように配慮する必要があります。
- 受診費用の負担: 健康診断の費用は、原則として事業者が負担しなければなりません。
- 健康診断結果に基づく事後措置: 健康診断の結果、異常が見つかった労働者に対しては、医師や保健師と連携し、適切な事後措置を講じる義務があります。これには、精密検査の受診勧奨、保健指導、必要に応じた就業上の配慮などが含まれます。
- 労働者への結果通知と説明: 健康診断の結果は、速やかに労働者に通知し、医師や保健師による説明の機会を設けることが望ましいです。
- 個人情報の保護: 健康診断の結果は、非常にデリケートな個人情報であるため、厳重な管理と保護が求められます。
ただし、法令で定められている定期健康診断の項目は必要最低限の検査項目であるため、法定項目にがん検診などの項目を組み合わせて実施している企業も多くあります。また、生活習慣病予防健診など指定の項目で実施する健康診断に対して補助金制度などを設けている健康保険組合も多くありますので、それらの制度を活用することで費用を抑えつつ検査項目を充実させることも可能になります。ご加入されている健康保険の健康診断制度について、ぜひ一度確認してみましょう!
労働者にとっての意義
これらの健康診断は、労働者自身の健康を守る上でも極めて重要です。
- 疾病の早期発見: 自覚症状がない段階で、生活習慣病などの病気の兆候を発見できる可能性があります。
- 健康意識の向上: 自身の健康状態を把握することで、生活習慣を見直すきっかけになります。
- 安心して働ける環境: 企業が労働者の健康に配慮していることを実感でき、安心して業務に取り組むことができます。
職場の健康診断(事業者健診)における安全配慮義務や自己保健義務についてはこちらの記事で解説しています
事業者健診における安全配慮義務と自己保健義務とは?
まとめ
労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条・44条は、労働者の健康を守るための日本の法制度の重要な柱です。これらの規定を遵守することは、企業の社会的責任であるだけでなく、労働者の健康と安全を確保し、ひいては企業の生産性向上と持続的な発展に繋がる不可欠な取り組みです。
企業は、これらの法令の趣旨を深く理解し、単なる義務としてではなく、労働者の健康を積極的に支援する姿勢で健康管理に取り組むことが求められます。そして、労働者自身も、自身の健康を守るために積極的に健康診断を受診し、結果を活用することが大切です。