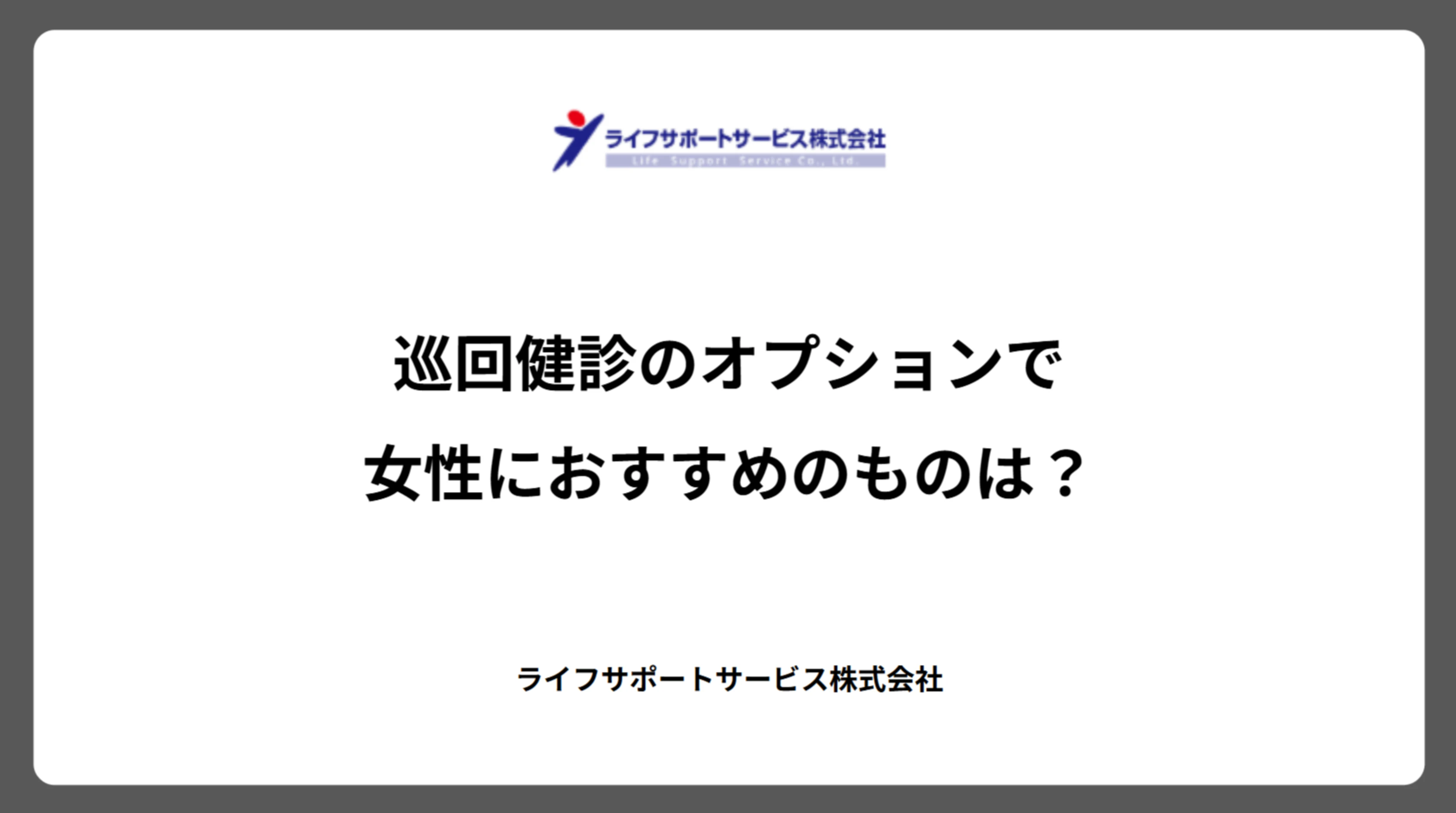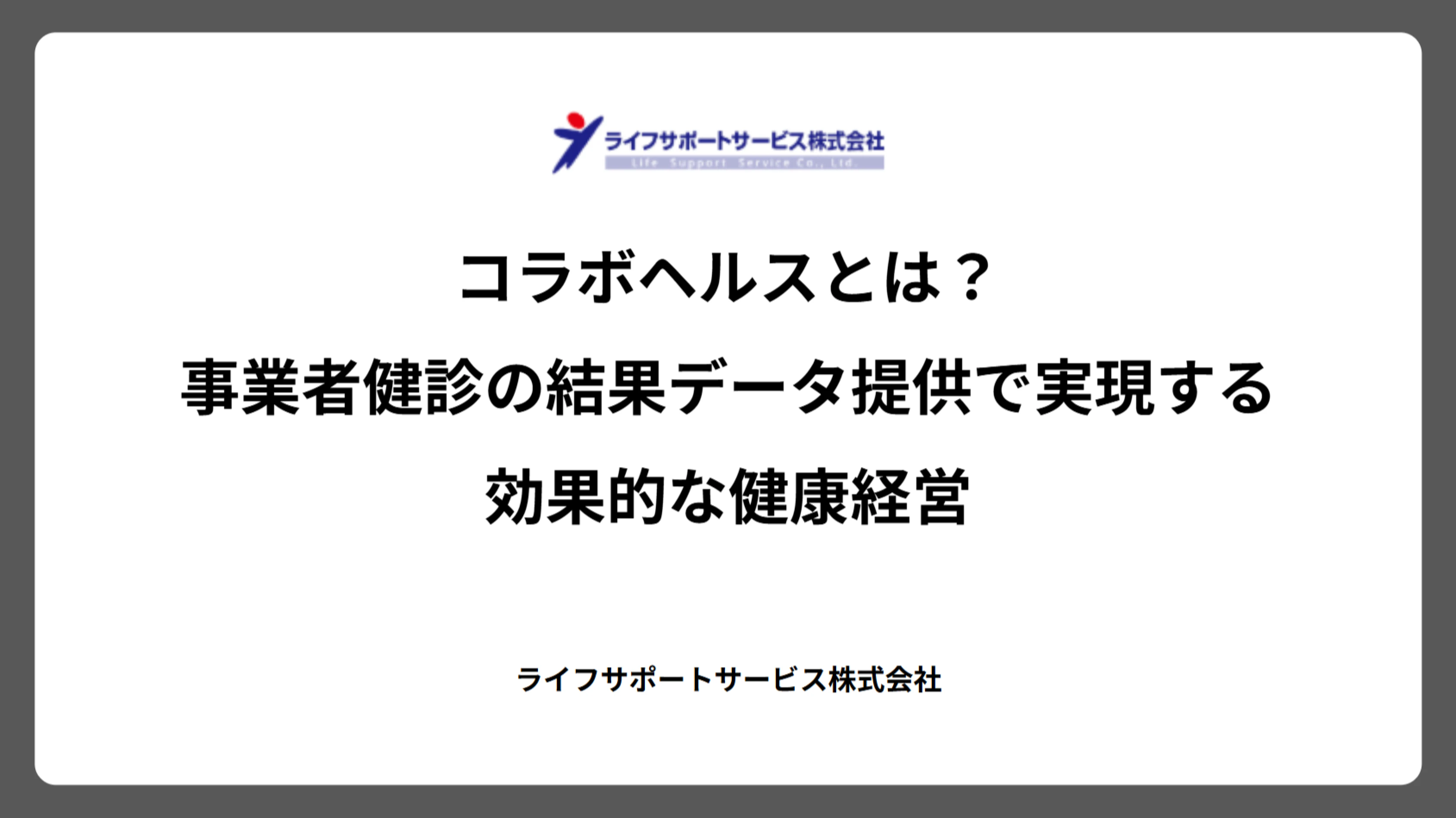記事公開日
最終更新日
健康診断の受診率を上げる方法とは?巡回健診など、健康管理担当者が実践すべき5つの工夫

健康経営への関心が高まるなかで、企業や団体にとって、健康診断の「受診率向上」は避けて通れない課題となっています。
特に総務部などの健康管理担当者は、社員の健康を守ると同時に、労働安全衛生法に則った実施義務も担っており、その責任は重大です。
近年では、健康診断の受診率が思うように伸びないことに悩む企業も少なくありません。
受診率が低いまま放置すれば、健康リスクの早期発見が遅れ、結果的に労務リスクや企業イメージの低下にもつながりかねません。
この記事では、「健康診断の受診率を上げる」ための具体的な5つの工夫を中心に、受診率向上に寄与する施策をわかりやすく解説いたします。
健康診断の受診率が重要視される背景
法的義務と企業リスク
日本国内において、事業主には労働安全衛生法に基づき、従業員に対して年1回の定期健康診断を実施する法的義務があります。
特に常時使用する労働者に対しては、「雇い入れ時」と「定期的な診断」が義務付けられており、企業がこれを怠った場合、罰則が科される可能性もあります。
また、健康診断を受診しなかった従業員が後に重大な健康トラブルを発症した場合、企業の安全配慮義務違反として法的責任を問われるケースも存在します。
したがって、単なる「制度としての実施」にとどまらず、「実際に受診されているか」という観点、すなわち受診率の向上が、企業リスクを軽減する上で極めて重要なのです。
「労働安全衛生法」や「安全配慮義務」に関する関連記事
職場の健康診断に関する法律:労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条・第44条の重要性
事業者健診における「安全配慮義務」と「自己保健義務」とは?
健康経営やESG投資との関連性
近年では、従業員の健康管理に積極的に取り組む「健康経営」の重要性が高まっています。
これは企業価値の向上や生産性の維持・向上につながるだけでなく、投資家や金融機関からの評価基準としても注目されています。
特に、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の観点から評価されるESG投資では、「従業員の健康管理」が「社会(S)」における重要な評価項目の一つとされており、健康診断の受診率もその評価に含まれる可能性があります。
このように、健康診断の受診率を上げることは、法的義務の履行のみならず、企業のブランディングや持続可能性、外部評価においても無視できない要素になっているのです。
健康診断の受診が進まない主な理由
企業や団体が健康診断を実施しているにもかかわらず、実際の受診率が思うように伸びない…。これは多くの総務担当者が直面する共通の課題です。
では、なぜ健康診断の受診が進まないのでしょうか。その主な理由を見ていきましょう。
業務都合によるスケジュール調整の難しさ
特に現場勤務や営業職の従業員にとって、決められた日程・場所での受診は負担になりやすく、業務との兼ね合いから参加を見送るケースもあります。
多忙な時期に重なれば、「後で受けよう」と考えたまま、最終的に受診しなかったという結果に陥ることも少なくありません。
健康診断の重要性に対する理解不足
健康診断の目的や必要性が十分に周知されていないと、社員自身が「自分は元気だから大丈夫」「何かあったらそのときに対処すれば良い」と受診の優先度を下げがちです。
特に、若年層の社員に多く見られる傾向であり、定期健診を“義務”ではなく“任意”のように捉えてしまう要因にもなっています。
会場へのアクセスや受診環境の不便さ
受診会場が遠方だったり、手続きに時間がかかったりすることが、心理的なハードルとなる場合もあります。
特に地方の拠点や小規模オフィスでは、都市部のような利便性が確保されておらず、「わざわざ健康診断を受けに行く」負担が敬遠される原因となり得ます。
プライバシーや結果への不安
健康診断を受けた結果が会社に知られることを嫌がる社員もいます。
「再検査や指導を受けたら、評価に影響するのではないか」「自分の病歴が共有されるのでは」といった懸念が受診回避の動機となることもあるため、プライバシーの保護に対する明確な方針も重要です。
制度の形骸化と実施側の意識不足
総務部門として「制度を整備すれば役割を果たしている」と考えてしまうと、受診促進のための周知活動やフォローが手薄になります。
その結果、社員側も重要性を感じられず、結果的に受診率が低迷してしまうという悪循環に陥りがちです。
このような課題を踏まえると、健康診断の受診率を上げるためには、制度設計だけでなく「現場目線」「社員目線」での工夫が不可欠であることがわかります。
健康診断の受診率を上げるための5つの工夫
健康診断の受診率を高めるには、単に「制度を整える」だけでは不十分です。
現場の状況や従業員の心理に寄り添った工夫を加えることで、初めて効果的な受診促進が実現します。
ここでは、総務担当者がすぐに実践できる5つの具体的な取り組みをご紹介します。
1.社内周知と啓発の強化
まず取り組むべきは、健康診断の意義を社内にしっかり伝えることです。
目的が明確でないまま「日程だけ通知される」と、従業員にとっては単なる業務の一環でしかありません。
健康診断が従業員自身の健康維持や早期発見につながる重要な機会であることを、具体的なデータや過去の事例などを用いて伝えることで、「受ける理由」が明確になります。
また、経営層からのメッセージや社内イントラでの啓発コンテンツの配信も効果的です。
2.日程・会場(医療機関)の柔軟な設定
業務多忙な社員にとって、「決められた1日だけの健診日程」では都合がつかないこともあります。
複数日程の設定や、午前・午後など時間帯の選択肢を増やすことで、受診のハードルを下げられます。
さらに、会場についても、本社や主要拠点だけでなく、地方支店や営業所ごとのニーズに合わせた会場(医療機関)を設定することが重要です。
勤務時間内に受けられるよう調整(健康診断受診を勤務時間と認定)することで、受診率の向上が期待できます。
3.巡回健診の導入
特に拠点が分散している企業や団体には、「巡回健診」の導入が効果的です。
巡回健診とは、医療機関のスタッフが職場まで出向いて健康診断を実施するもので、受診者は移動の手間がなく、業務の合間にも気軽に受けられるのが特徴です。
巡回健診を導入することで、従来受診率が低かった拠点でも改善が見込めます。
また、総務部門にとっても予約管理や集計の効率化につながり、事務負担の軽減にも寄与します。
「巡回健診」に関する関連記事
巡回健診とは?受診率は上がる?施設健診との違いやメリット、デメリットを解説
4.インセンティブ制度の活用
受診に対する「ちょっとしたご褒美」がモチベーションになることもあります。
たとえば、受診者に対してクオカードや社内ポイントを付与する、福利厚生メニューと連動させるなど、インセンティブの活用は有効な手段の一つです。
ただし、制度設計の際は公正性や不公平感の回避にも注意が必要です。
あくまで「全員が受診しやすい」環境整備の一環として活用する視点が大切です。
5.デジタルツールによる受診管理
健診の申込状況や未受診者の管理には、Excelなどの手作業では限界があります。
そこでおすすめなのが、クラウド型の健診管理ツールや社内ポータルとの連携です。
受診予約・リマインダー・結果通知などを一元管理できる仕組みを導入することで、総務側の手間が大幅に削減され、従業員も「受け忘れ」を防げるようになります。
結果的に、全体の受診率の底上げにつながる施策と言えるでしょう。
健康診断後に行うべきフォロー体制
健康診断は受けたら終わりではありません。
健診結果を踏まえた適切なフォローアップを行うことで、従業員の健康維持・増進に結びつけることができ、結果的には企業全体の生産性向上にも寄与します。
ここでは、健康診断後に総務部門が実施すべき基本的な対応を紹介します。
再検査の促し方
健診結果で「要再検査」や「要精密検査」とされた従業員には、早期の受診を促すことが極めて重要です。
放置すれば、症状が進行し、重篤な健康問題につながる可能性があるためです。
再検査の案内は、できるだけ丁寧かつ個別に行うのが望ましく、「いつまでに受診を」「どのような医療機関が対象か」など、具体的な情報を付け加えると従業員の行動につながりやすくなります。
また、再検査を受けたかどうかを後追いできる仕組みを社内に整えることも、フォロー体制の一環として重要です。
加えて、プライバシー保護への配慮も忘れてはなりません。
特定の部署で健康状態が把握できるようになっている場合、情報の取り扱いや通知方法に十分な注意を払いましょう。
健康指導や面談の実施例
健診結果に応じた「健康指導」や「保健師・産業医との面談」も、健康リスクの早期対処に有効です。
特に生活習慣病の予備軍とされる従業員に対しては、継続的なフォローによって行動変容を促すことが期待されます。
企業によっては、健康管理システムと連携し、面談記録や健康指導内容をデジタル管理しているケースもあります。
これにより、次回の健診や保健活動に活かせるデータの蓄積が可能になります。
また、「食事指導」「運動アドバイス」「ストレスケア」など、専門家によるオンライン健康相談サービスを導入している企業も増えつつあります。
こうした取り組みは、従業員からの信頼感を高め、企業の健康経営に対する姿勢を内外に示す機会にもなります。
このように、健康診断後のフォローアップ体制を整備することは、単なる業務対応ではなく、企業としての健康管理姿勢を問われる重要なポイントです。
健診後の「事後措置」に関する関連記事
職場の健康診断後の「事後措置」はなぜ重要? 労働者の健康と企業の義務、理解しておくべきポイントを徹底解説
まとめ
健康診断の受診率を向上させることは、単なる「法的義務の履行」にとどまらず、企業の持続可能性や従業員満足度、さらには外部からの評価にも直結する重要な取り組みです。
社内啓発や柔軟なスケジューリング、巡回健診の導入、インセンティブ制度、デジタル管理など、いずれの施策も「社員にとって受けやすい環境づくり」が共通のテーマです。
加えて、健診後のフォロー体制も忘れてはなりません。
再検査の案内や健康指導を徹底することで、従業員の健康リスクを低減できるだけでなく、健康経営の実践にもつながります。
「健康診断の実施=受診完了」ではなく、「受診率の向上とその後の健康支援」までをトータルで捉える視点こそが、これからの総務部門に求められる姿勢です。
社員の健康を守ることは、企業の未来を守ること。総務部門の一歩が、健全で安心な職場づくりの第一歩となります。
ライフサポートサービスでは埼玉県内を企業・団体を中心に巡回健診や健康管理業務をサポートしています
巡回健診・集団健診 | ライフサポートサービス株式会社